2020年の民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと大きく変化しました。
これにより、不動産売却時に売主が負うべき責任の内容や対応方法が大きく見直されたんですね。
知らずに契約すると後から大きな損害を被ることにもなりかねませんので、事前の理解がとても大切ですよ。
本記事では、契約不適合責任の基礎から売主の義務、免責の条件、そして契約時に注意すべきポイントまで、弁護士監修のもとで詳しく解説していきますね。
不動産売却を検討している方は、ぜひ最後までご覧くださいね。
この記事を読むとわかること
- 契約不適合責任の基本と瑕疵担保責任との違い
- 不動産売却時に売主が負う4つの法的義務
- 免責条件の有効性と無効となる具体例
不動産売却時の契約不適合責任とは?売主がまず知るべき基本
まず最初に、「契約不適合責任」とは何かについて整理しておく必要がありますね。
従来の「瑕疵担保責任」から制度が変わったことで、売主が負う法的責任の考え方も大きくシフトしたんですよ。
この章では、制度の変遷や定義、そして売却時にどう影響してくるのかを解説していきますね。
特にこれから不動産を売却する方は、ここでの内容を押さえることがリスク回避の第一歩になりますよ。
それでは、順を追って確認していきましょう。
瑕疵担保責任との違いを理解しよう
瑕疵担保責任は、売買契約の対象となる物件に「隠れた瑕疵」があった場合に適用されるものでしたね。
これに対し契約不適合責任では、「隠れているか否か」に関係なく、契約内容と適合しない場合すべてが対象となる点が異なりますよ。
具体的には、種類・品質・数量が契約と異なる場合に責任が発生する仕組みです。
これにより、売主側の注意義務や開示義務がより明確化されているんですね。
つまり、物件を現状で売るという姿勢だけでは不十分な時代になったということですよ。
対象となる「種類・品質・数量」の具体例
たとえば、種類については「マンションの1LDKを売るはずが、2Kが引き渡された」ようなケースが該当しますね。
品質の不適合では、「建物に雨漏りがある」「配管が腐食していた」などの例が挙げられますよ。
数量では、「登記簿上100㎡の土地だったが、実測で90㎡しかなかった」などが典型例ですね。
このようなズレがある場合には、買主から修補や減額、損害賠償などを請求される可能性がありますよ。
売主は、引き渡し前の段階でこうした不適合がないかを十分に確認しておく必要があるんですね。
契約不適合責任で売主が負う4つの義務

契約不適合責任では、売主に対して具体的な4つの責任が課されます。
それが「追完請求」「代金減額請求」「損害賠償請求」「契約解除請求」ですね。
これは買主の救済手段として民法に明文化されています。
売主はその請求に応じる義務を負う形です。
これらはすべて買主が状況に応じて選択できるもので、売主としてはどのような主張が来ても対応できる準備が求められますよ。
以下で、それぞれの請求内容について詳しく説明していきますね。
不動産売却をスムーズに進めるためにも、しっかり把握しておきましょう。
追完請求(修補・代替物の提供)
追完請求とは、契約通りの状態にするよう売主に求める権利ですね。(民法562条)
たとえば、キッチン設備が契約と違っていた場合には、修理や交換が求められるケースがありますよ。
このような請求があった場合、売主は速やかに修補や代替品の提供を行わなければなりませんね。
追完は、基本的には買主が請求方法を選べる仕組みになっていますよ。
ただし、売主に過度な負担がかかる場合には、別の方法での追完も認められる場合がありますね。
代金減額請求への対応
追完が行われなかったり不能な場合には、買主は代金の減額を請求できるんですよ。(民法563条)
たとえば雨漏りの修補が間に合わない場合などには、その分の価値を差し引くような対応が求められますね。
代金減額請求は、あくまで契約不適合が明確である場合に限って有効となりますよ。
請求が妥当かどうかは、契約書や状況証拠をもとに判断されますね。
売主としては、書面で契約内容を明示しておくことで不必要な減額を防ぐことができますよ。
減額や再交渉を見越すなら、最初の“売り出し価格”設計が要です。
売却価格の決め方5ステップ|相場×目的で“損しない”価格設計
損害賠償請求が来るケースとは?
契約不適合により損害が生じた場合、買主はその損害分の賠償を求めることができるんですよ。
たとえば、建物の不具合によって家財が破損した場合や、修理費用が発生したケースなどが該当しますね。
売主に過失がなかった場合でも、一定の責任を負うリスクがありますよ。
ただし、免責事由が成立する場合には請求を回避することも可能ですので、後述の免責条件をよく確認してくださいね。
契約書に責任範囲を明示しておくことが、トラブル回避には重要になりますね。
契約解除されるリスクとその要件
不適合の程度が重大で、契約目的が達成できないと判断される場合には、契約そのものが解除されることがありますね。(民法541・542条・564条)
たとえば、建物の基礎部分に欠陥があり安全に居住できない場合などが該当しますよ。
このようなケースでは、買主は全額返金を求めることが可能になりますね。
売主にとっては非常に大きな損失となるため、事前の点検と契約内容の確認が極めて重要ですよ。
また、解除を防ぐために代替手段を事前に提案できるよう備えておくと良いですね。
無理な“高額前提”は売れ残り→トラブルの連鎖を招きがちです。
見極め基準を先に確認しておくようにしましょう。
免責される条件とできない条件の違いとは?
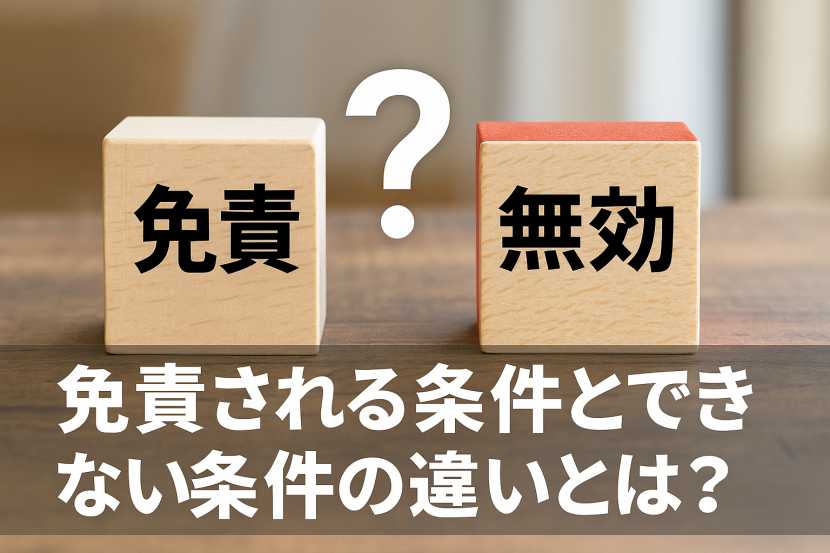
契約不適合責任には、一定の条件下で免責される余地があるんですね。
しかし、すべてのケースで免責が認められるわけではありませんので注意が必要ですよ。
この章では、どのような特約が有効で、どのような内容が無効となるかを明確に解説していきますね。
免責条件をしっかり理解しておくことで、売主としてのリスクヘッジが可能になりますよ。
契約書作成時の参考にもなりますので、ぜひ押さえておきましょう。
免責特約は原則有効だが万能ではない
民法上は、契約自由の原則に基づいて、契約不適合責任の免除特約を設けることが可能とされていますね。
ただし、それが消費者契約や宅建業法の制限に反する場合は無効になりますよ。
有効な免責特約の一例として、「2年以内に通知がない限り免責とする」といった条件付きのものがありますね。
一方で、「すべての責任を免除する」などの一方的すぎる条項は認められないことが多いですよ。
売主としては、相手が誰であるか(個人か業者か)によって契約条項を調整する必要がありますね。
「売主が知っていた」場合は免責不可
売主が契約不適合の事実を知っていた、または重大な過失により知らなかった場合は、免責されませんよ。
これは、売主の誠実性を担保するための重要なルールなんですね。
故意または重過失があるとみなされた場合には、どれだけ免責特約があっても効果を持たないことになりますよ。
そのため、売却前の調査や説明義務を怠らないことが最も重要なんですね。
リスクを避けるためにも、物件の状態を正確に把握し、契約書でしっかりと記載しておく必要がありますよ。
「買主が業者」の場合は免責が成立することも
買主が不動産業者である場合には、民法や宅建業法の保護規定が適用されませんので、免責条項が有効に機能するケースがありますね。
つまり、業者間取引においては、売主が契約不適合責任を一切免除する条項を盛り込むことも可能ということですよ。
このような取引では、互いの専門性が前提となっているため、一般消費者保護の観点が緩和されるんですね。
ただし、免責が可能だからといって説明責任を怠ると信頼を損なう可能性もあるため、注意が必要ですよ。
業者間でも紛争を避けるためには、契約条項を丁寧に詰めることが大切ですね。
民法・宅建業法・消費者契約法による制限

契約不適合責任に関しては、民法以外にも宅建業法や消費者契約法といった法律の制限がかかることがありますよ。
特に個人が買主となるケースでは、これらの法律によって売主に不利な免責特約が無効となる可能性があるんですね。
この章では、それぞれの法律がどのように売主の対応に影響を及ぼすかを見ていきますね。
実務上のトラブルを避けるためにも、法律ごとのルールを理解しておく必要がありますよ。
特に宅建業者として売主になる場合は、これらの法律を無視できないですね。
宅建業者は2年以上の責任期間が義務
宅建業者が売主となる不動産売買において、買主に不利となる契約不適合責任の特約は原則として無効になりますね。
契約不適合責任の通知期間を「引渡しから2年未満」とする条項は無効とされる点に注意が必要ですよ。
売主が宅建業者である場合は、少なくとも2年以上の契約不適合責任を負わなければなりませんね。
それ以下の期間で契約書を作成しても、法的には買主に不利な無効な内容となるため意味がありませんよ。
そのため、契約書を作成する際は宅建業法第40条の規定を必ず確認しながら進めることが大切ですね。
消費者契約法で無効になる特約の例
消費者契約法では、事業者が消費者と契約する際に、損害賠償責任を一方的に免除する特約は無効とされていますね。
「いかなる場合でも売主は責任を負わない」といった条項は、消費者契約法に反するため効力を持たないですよ。
また、「損害賠償額の上限を◯◯円までとする」といった制限も、場合によっては無効になる可能性がありますね。
このような規定に違反すると、トラブル時に売主が不利な立場に立たされる可能性があるので注意が必要ですよ。
消費者が相手の場合は、特約を設ける前に法律のチェックを忘れないようにしたいですね。
新築住宅は10年保証が義務づけられるケースも
新築住宅を販売する場合、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて10年間の瑕疵担保責任を負うことになりますね。
対象となるのは、構造耐力上主要な部分と、雨水の侵入を防ぐ部分ですよ。
この規定は任意ではなく強制適用されるため、売主が契約で免除することはできないんです。
つまり、新築住宅の場合は契約不適合責任のうち一部は、必ず10年間責任を負わなければならないということですね。
売主が業者であるかどうかにかかわらず、この義務は適用されますので、該当物件を販売する際は必ず事前確認が必要ですよ。
契約書に入れるべき文言例と注意点

契約不適合責任に関するトラブルを回避するためには、契約書の文言を慎重に設計する必要がありますね。
曖昧な表現では、あとから責任の所在が不明確になり、紛争に発展するリスクがあるんですよ。
売主としては、自らに有利な条項を盛り込みつつも、法律違反にならないようにバランスを取ることが重要ですね。
この章では、売主と買主の両方の立場における文例を紹介しながら、注意点についても解説していきますね。
実際の契約書に取り入れる際の参考にしていただければと思いますよ。
売主に有利な契約条項の作り方
売主としては、自身の責任を必要最低限に抑えつつ、法令に適合する契約書を作成することが重要ですね。
例えば、「契約不適合があった場合には、売主が修補、減額、損害賠償のうちいずれかを選択して対応する」と明記する方法がありますよ。
また、通知期限を「引渡し後2年以内」と設定することで、宅建業法上の制限もクリアしつつ、責任の範囲を明確にできますね。
さらに、想定外の請求を避けるために「買主による修理・改修は事前同意が必要」といった条件も加えると良いですよ。
ただし、極端な免責条項や一方的な条件は消費者契約法に反する可能性があるので注意が必要ですね。
買主にとって不利とならないよう配慮すべきこと
買主の立場では、自身の権利を十分に確保できる条項が盛り込まれているかどうかを確認することが大切ですね。
たとえば、「契約不適合が判明した場合には、買主の判断で追完または代金減額を請求できる」といった表現が望ましいですよ。
また、通知期間が極端に短いとリスクになりますので、「契約不適合を知った時から1年以内」とする条項が入っているか確認しましょう。
容認事項についても、不利な内容が含まれていないか事前にしっかりチェックすることが必要ですね。
契約の段階でしっかり交渉しておくことで、将来的なトラブルを回避できるようになりますよ。
契約不適合責任に関する不動産売却のまとめ
契約不適合責任は、2020年の民法改正によって「瑕疵担保責任」から大きく見直された制度ですね。
不動産売却を行う売主は、この新制度に基づく責任をしっかり理解しておく必要がありますよ。
売主が負う責任は多岐にわたり、免責条件も法令や契約の内容次第で大きく変わる点が特徴です。
宅建業法や消費者契約法などの制限もあるため、契約書の作成には専門家のアドバイスを受けるのが安心ですね。
2025年以降も法律改正が続く可能性がありますので、最新情報を常にチェックしながら、リスク回避を徹底していきましょうね。
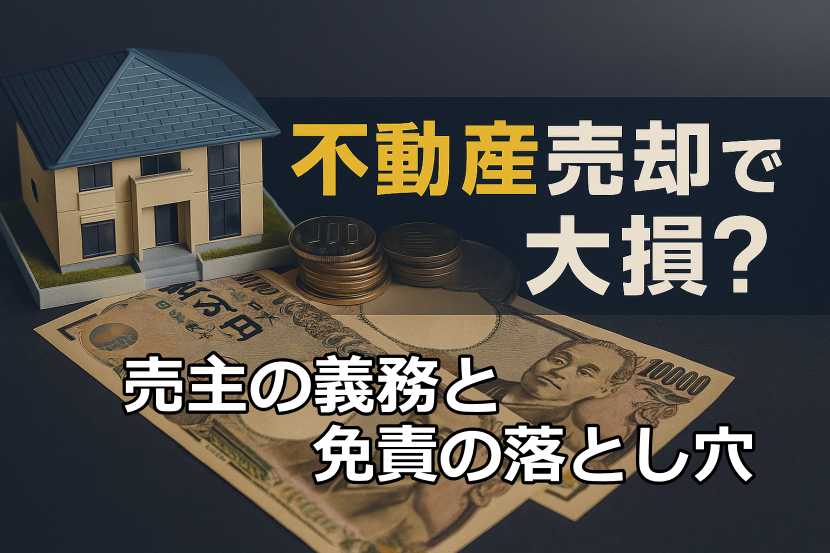


コメント