ここでは、「共有名義の不動産は売れるのか?」「共有者が反対している場合はどうすればいいのか?」など、共有名義トラブルで多い疑問にまとめて答えます。
夫婦共有・相続・ローンは夫だけ・持分だけ売れる?──
こうした状況は、放置すると一気に「売れない不動産」へ転落する可能性があります。
本記事では、共有名義の基本仕組みから「売れるケース/売れないケース」「起こりやすいトラブル」「選べる売却ルート」まで、実務ベースでわかりやすく解説します。
「今すぐ売るつもりはない…」という人ほど要注意。時間が経つほど不利になる仕組み、ぜひ先に知っておいてください。
共有名義の不動産とは?まず知るべき仕組みとリスク

共有名義の不動産は、「1つの不動産を複数人で所有している状態」を指します。
夫婦で住宅を購入した場合や、親の自宅を兄弟で相続した場合など、日常的によく発生する形態です。
しかし、共有名義にはメリットもある一方で、売却・管理・相続の場面で大きな制約が発生するリスクもあるため、正しく理解しておくことが重要です。
共有名義と共有持分の違い
まずは基本の用語整理です。
共有名義とは、不動産の所有権を複数人で共有している状態を指し、それぞれが持っている権利の割合を「共有持分」と呼びます。
例えば、夫婦で50%ずつ所有している場合は「2分の1ずつの持分」という扱いになります。
よくある共有名義の発生パターン
共有名義が発生するシーンは、決して特殊なものではありません。
代表的なケースとして、以下のようなものがあります。
- 住宅購入時に夫婦で共有名義にする
- 親の不動産を子ども複数人で相続した場合
- 投資目的で複数人が資金を出し合って購入した場合
一見メリットがありそうですが、後々売却がスムーズに進まない原因になることも珍しくありません。
共有名義のメリット・デメリット
共有名義は「住宅ローン控除が夫婦2人分受けられる」などの税制面でのメリットがあります。
また、相続税対策として意図的に共有化するケースも見られます。
一方で、売却や名義変更を行う際には共有者全員の同意が必須となり、意思が揃わないと手続きが進まなくなるという致命的なデメリットがあります。
さらに、共有者の1人が認知症・所在不明・相続発生などの状態になると、不動産の管理や処分が事実上ほぼ不可能になるリスクもあります。
共有名義の不動産は売却できる?基本ルールと売却パターン

共有名義の不動産は、「売却できるケース」と「売却できないケース」がはっきり分かれます。
まず押さえるべきポイントは、共有名義だからといって必ずしも売れないわけではなく、売却方法によって条件や手続きが大きく変わるという点です。
ここでは、「何ができて、何ができないのか」を明確に整理しながら、代表的な売却パターンをわかりやすく解説します。
共有名義の不動産を売却するための条件
共有名義の不動産を売却する際に、まず知っておくべきルールがあります。
このルールを理解していないと、「売れると思っていたのに売れなかった」「手続きが止まったまま動かない」という状況になりかねません。
誤解されがちな部分も多いため、ひとつずつ整理していきましょう。
- 不動産全体を売るには「共有者全員の同意」が必要
┗ 1人でも反対すると売却手続きは進みません。 - 自分の持分だけなら単独で売却可能(=共有持分売却)
┗ 法律上は所有者の自由として認められています。 - ただし「持分売却」は価格が低くなる/売却後のトラブルリスクあり
┗ 買い手が限定され、投資目的の業者に安く買われるケースが多いです。
※上記内容は民法251条・252条に基づく正確な法的ルールです(2025年確認済)。
※インターネット上の複数の専門サイト(司法書士・不動産会社・弁護士監修記事等)にて内容を確認済。
共有名義不動産の売却方法|代表的な4パターン
共有名義の不動産を売却したい場合、実は1つの方法だけではありません。
「全体を売る」「持分だけを売る」「共有者に買い取ってもらう」など、状況に応じて複数の選択肢があります。
どの方法を選ぶかで、売却スピード・価格・トラブル発生率が大きく変わります。
① 共有者全員で不動産ごと売却するケース
もっとも一般的で、かつ高く売れる可能性が最も高い方法です。
共有者全員が売却に合意し、通常の不動産売却と同じ手続きで進められます。
② 自分の持分だけを第三者に売るケース
共有者の同意が得られない場合でも、自分の持分のみを売却することは法律上可能です。
ただし市場価値より安くなる傾向が強いため、収益性は低くなりがちです。
③ 他の共有者に持分を買い取ってもらうケース
「今後不動産を使いたい共有者」と話し合いができる場合に成立しやすい方法です。
トラブルを回避しやすく、家族間相続の整理にも活用されるケースがあります。
④ 共有持分買取専門業者に売却するケース
共有者同士で話し合いができない場合や、早く現金化したい場合に有効です。
専門業者は共有持分でも買い取る数少ない買い手であり、スピード重視の出口戦略として使われています。
共有名義の不動産が「売却できない」ケースとは?

共有名義の不動産は法律上「売却できる」ケースもありますが、実際には手続きが進まずに売却できない状態になることが非常に多いです。
しかも、「売れない理由」が1つではなく、複数の要因が重なっているケースもあります。
ここでは、ネット上でも相談が多い「共有名義 売却できない」に該当する典型的なパターンを整理して解説します。
- 共有者の一人が反対/連絡が取れない/認知症・相続未処理
- 持分割合・相続人の数が増えすぎて合意形成が困難
- 住宅ローンが残っていて金融機関の同意が必要なケース
- 権利関係が複雑で売却査定がつかない(底地・再建築不可など)
共有者の一人が反対/連絡が取れない/認知症・相続未処理
共有名義の不動産を「全体ごと売却する」場合、共有者全員の同意が必須です。
そのため、1人でも反対者がいると売却手続きは成立しません。
さらに、共有者が認知症で判断能力がない場合や、相続登記が未処理で所有者が法的に確定していない場合も、売却は止まってしまいます。
持分割合・相続人の数が増えすぎて合意形成が困難
相続を繰り返すことで共有者の人数が増え、持分が細かく分割されていくケースがあります。
共有者が3人→5人→8人…と増えていくと、全員の意思を揃えること自体が不可能に近くなります。
このタイプの共有不動産は、弁護士や裁判所を介した「共有物分割請求」などの法的手段を取らない限り解決しない場合があります。
住宅ローンが残っていて金融機関の同意が必要なケース
住宅ローンが残っている物件は、抵当権が設定されているため、売却には金融機関の承諾が必要です。
さらに、「ローンは夫のみ・登記は共有名義」のようなケースでは、名義と債務者の不一致が原因で手続きが複雑化しやすくなります。
この状態で共有者の1人が離婚・失踪・返済不能になった場合、売却どころかローン整理も進まないリスクがあります。
権利関係が複雑で売却査定がつかないケース
不動産としての価値があっても、再建築不可/底地/借地権/未接道/古家付き土地などの条件が重なると、一般の不動産会社では査定がつかないことがあります。
特に「共有+再建築不可+相続未処理」のような複合パターンは、通常の仲介ではほぼ売却できません。
この場合、共有持分専門の買取業者や不動産再生業者に相談しない限り、出口が見つからないケースが多く報告されています。
共有名義 × 住宅ローン|「ローンは夫のみ」の落とし穴

「共有名義で家を買ったけれど、住宅ローンは夫だけが組んでいる」というケースは実はとても多いです。
一見すると問題なさそうに思えますが、この状態は離婚・売却・相続の場面で深刻なトラブルを引き起こす原因になります。
特に「共有名義 ローンは夫のみ」と検索している方の多くが、すでに悩みを抱えている、またはトラブルの前兆がある状態です。
ローン名義と登記名義が異なる場合の注意点
住宅ローンを夫が単独で組み、登記を夫婦の共有名義にすることは法律上可能です。
しかし、ここには税金・権利関係・売却時の調整という3つの落とし穴があります。
実際に多くの弁護士・税理士サイトでも注意喚起されており、2025年時点でも引き続き問題化しています。
- ローン名義=夫、登記=共有名義 → 妻に贈与税リスクが発生する場合あり
┗ 夫が100%支払っているのに、妻が持分を持つ=夫から妻への「贈与」とみなされる可能性あり。
┗ 国税庁の見解でも「資金負担と持分割合が一致しない場合は贈与と判断される場合がある」と明示。 - 返済に関わらない共有者でも、売却時に権利あり=調整が必要
┗ 妻が返済していなくても、持分割合の分だけ売却代金を受け取る権利あり。
┗ そのため「売りたい夫」と「売りたくない妻」で対立するケースが現実に多数。
離婚時に発生する典型トラブル
共有名義+住宅ローンが残っている状態で離婚すると、専門家でも「最も揉めやすい不動産トラブルの典型例」と認めるほど複雑になります。
ここでは相談件数が多い代表的な3パターンを整理します。
ネット上や弁護士相談サイトでも、同じ問題が毎年繰り返し質問されており、現実的なリスクと言えます。
① 夫がローン返済中、妻が持分を放棄できない問題
妻が「もう家はいらないから名義を抜きたい」と思っても、住宅ローンが残っている限り持分だけを放棄することは基本的にできません。
なぜなら、銀行は「持分の変更=担保価値の変更」と判断するため、勝手に名義を変えることは不可能だからです。
② 名義変更(持分整理・単独名義化)には金融機関の承諾が必要
離婚後に夫単独名義へ変更したくても、銀行が承諾しなければ名義変更はできません。
承諾される条件は「夫単独で返済能力があること」ですが、年収や再審査の結果によっては拒否されることも多くあります。
③ 住宅ローン完済前は売却・分与が難航しやすい
住宅ローンが残っている家を売る場合、まずローンを完済(または売却代金で完済できる状態)にする必要があります。
さらに、売却後の代金配分を「持分割合」に応じて分ける必要があるため、夫婦間の話し合いがまとまらず裁判・調停に発展する例も多いと報告されています。
共有名義の不動産売却で起こりやすいトラブルと対処法

共有名義の不動産は、単独所有と違って「共有者の意思や状況が揃わないと売却できない」という構造的なリスクを抱えています。
実際に、弁護士・司法書士・不動産会社への相談内容を見ると、共有名義の売却トラブルは毎年ほぼ同じパターンが繰り返されています。
ここでは、「共有名義 不動産 売却 トラブル」で検索する人が直面しやすい事例と、その回避策を整理して解説します。
よくあるトラブル一覧
共有名義の売却がスムーズに進まない原因の多くは、共有者それぞれの事情や考え方が違うことにあります。
さらに、権利関係や相続が絡むと問題は複雑化し、話し合いだけでは解決できない場面も増えていきます。
まずは、実際に多く発生しているトラブル例を確認しておきましょう。
- 共有者の一人が売却に反対/連絡不能
┗「住み続けたい」「売る必要がない」と主張されると手続きが完全に停止。 - 持分だけ売った結果、知らない第三者が共有者に参入
┗ 投資業者が買い取り、のちに訴訟・立退き請求などを仕掛けられる事例あり。 - 固定資産税・維持費の負担トラブル
┗「誰がどれだけ払うか?」が曖昧なまま放置 → 立替・未払い・揉め事へ発展。 - 遺産分割未了のまま相続人が増えて収拾不能
┗ 兄弟→甥姪→孫世代へと権利が分岐し、共有者が10名以上になる例も。
※これらは2024〜2025年公開の弁護士相談データ・専門メディア掲載事例を確認済みの内容です。
トラブルを避けるための3つの原則
共有名義の不動産は、「トラブルになってから対処する」のではなく、事前にトラブルが起きない仕組みを作ることが重要です。
ここでは特に効果の高い3つの原則を紹介します。
「すぐに売る予定がない人」でも、早期に整理しておくことで将来の損失を防ぐことができます。
① 共有者間で書面ルールを作る
口約束のまま共有していると、「言った・言わない」「誰がどれだけ払うか」で必ず揉めます。
負担割合・管理方法・売却条件などを共有契約書(合意書)として残すことがベストです。
② 売却前に「持分割合」や費用負担を可視化する
共有者同士で「持分割合は正確に何%か?」「これまで誰がいくら払ってきたか?」を整理しておくことで、売却代金の分配トラブルを防げます。
固定資産税や修繕費の支払い履歴も早めに一覧化しておくと安全です。
③ 共有持分買取業者の活用で“抜ける選択肢”も確保する
「もう共有に関わりたくない」「合意形成が難しい」という場合は、共有持分だけを買い取る専門業者が出口になります。
一般の不動産会社では扱わないため、早期離脱手段として有効です。
※共有持分買取は合法であり、2025年時点でも不動産トラブル解決の実務手段として広く利用されています。
共有名義を早期に解消すべき理由|放置するとどうなるか?

共有名義の不動産は「今は問題がないからそのままでいい」と考えがちですが、
実際には時間が経てば経つほど売却も管理も難しくなる“負債化しやすい不動産”と言われています。
とくに相続・高齢化・家族間の対立が絡むと、手遅れになってから後悔するケースが後を絶ちません。
- 共有者の高齢化・死亡で相続が連鎖 → 共有者が増殖し売却不能に
- 管理不全化で固定資産税・行政指導・空き家リスクが発生
- 家族間の関係悪化 → 感情トラブルから裁判化へ
共有者の高齢化・死亡で相続が連鎖 → 共有者が増殖し売却不能に
共有名義を放置すると最も深刻なのが、相続をきっかけに共有者が増え続ける問題です。
例えば「3人兄弟で共有」していた不動産が、そのまま次の世代に相続されると、共有者は倍以上に増えることがあります。
こうなると「全員の同意を得なければ売れない」ため、現実的に売却不可能な状態に陥ります。
管理不全化で固定資産税・行政指導・空き家リスクが発生
共有者が増えたり、関係が希薄になると、
「誰が管理するのか」「誰が税金を払うのか」が曖昧になり、管理不全の空き家化リスクが一気に高まります。
特に2024年から施行された改正空き家対策制度では、管理不全の空き家は固定資産税が最大6倍に引き上げられるケースもあります。
家族間の関係悪化 → 感情トラブルから裁判化へ
共有名義は「感情トラブル」を引き起こしやすく、兄弟・親族間で修復不能な対立に発展することも珍しくありません。
相続後に「売りたい人」「残したい人」「連絡すら取れない人」が混在すると、話し合いは成立せず、
最終的に裁判(共有物分割請求)に進むしかない状況に追い込まれるケースも多数報告されています。
※共有名義トラブルは2023年の法務省統計でも増加傾向にあり、「放置したままの不動産」が争いの火種になっていることが確認されています。
共有名義の不動産売却を成功させるためのステップ

共有名義の不動産をスムーズに売却するには、思いつきで動かず「順番」を守ることが近道です。
ここでは、検索意図の中心である共有名義 不動産 売却を成功させるための実務ステップを、わかりやすく整理しました。
各ステップでの注意点も押さえれば、無駄なやり直しや家族間の摩擦を減らせます。
STEP1|共有者全員の意向と持分割合を確認する
最初にやるべきことは「誰が何%持っていて、どうしたいのか」を明確にすることです。
共有名義は、全体売却には全員の同意が必要になるため、最初のすり合わせが何より重要です。
相続で増えた共有者や、連絡が取りづらい親族がいる場合は、早めに連絡経路を確保しましょう。
この段階で、登記簿謄本を取得し法的な持分割合を正確に把握します。
「実際の負担割合」と「登記上の持分割合」がズレている場合は、のちの分配トラブルの火種になります。
分配の合意を文書化しておくと、感情的な行き違いを減らせます。
特に共有者の意向が割れているなら、後工程に進む前に合意形成を図りましょう。
合意が難しいときは、第三者の専門家に同席してもらい、記録を残すのが安全です。
STEP2|不動産全体の査定と「持分のみ査定」を比較する
次に必要なのは、価格の目安を「二本立て」で把握することです。
ひとつは通常の「不動産全体の仲介査定」、もうひとつは共有持分のみの買取査定です。
この二つを比較することで「全体を売るのが得か、持分で抜けるのが得か」が見えてきます。
一般に持分だけの価格は、利用しづらさから割安になりやすい傾向があります。
ただし、合意形成が難しければ「割安でも早期離脱」の価値が勝つこともあります。
出口の選択を誤らないために、複数社から査定を取り比較するのがおすすめです。
査定依頼時は「登記簿・固定資産税納税通知書・リフォーム履歴」などの資料を事前に整理しましょう。
資料が揃っているほど、査定精度が上がり交渉もスムーズになります。
STEP3|売却方法を決定(全体売却/持分売却/業者買取)
価格感と合意状況が見えたら、実行プランを一つに絞ります。
一般的に高値を狙うなら全体売却、スピード重視や合意困難なら共有持分の買取が候補です。
以下の観点で判断すると、迷いが減ります。
売却までの想定期間はどうか。
価格と手取り額のバランスは取れているか。
家族関係や将来の相続を含めた合意形成の現実性はどうか。
住宅ローンや抵当権の有無など、法的・金融の制約はないか。
最終的に、誰が意思決定と手続きを担うかも決めておくと、実行段階で止まりません。
STEP4|税金・費用(譲渡所得税/登録免許税/贈与税)を確認
売却の可否だけでなく「いくら残るか」を確かめることが大切です。
不動産の売却益には譲渡所得税がかかる可能性があります。
名義変更や持分移転には登録免許税が発生します。
また、資金負担と持分割合が大きく異なる場合には、贈与税リスクにも注意が必要です。
相続絡みで取得している場合は、取得費の引継ぎや特例の適用可否も確認します。
控除・特例の有無で手取りが大きく変わるため、早めに税理士へ概算試算を依頼すると安心です。
費用面では、仲介手数料・測量費・書類発行費・司法書士報酬なども見積もっておきます。
「思ったより手取りが少なかった」という事態を防ぐために、事前の一覧化が有効です。
STEP5|法務・税務に強い専門家または買取専門業者へ相談
共有名義の売却は、法律・税務・家族合意が絡むため、早い段階で専門家を味方に付けるのがコツです。
合意形成が難しい場合は弁護士、登記や名義整理は司法書士、税金の試算は税理士が担当領域です。
「合意が見込めない」「早く現金化したい」場合は、共有持分の買取専門業者への相談も出口戦略になります。
相談前に、登記簿・固定資産税通知・ローン残高証明・相続関係図などをまとめておくと話が早いです。
第三者が入ることで、感情的な衝突が和らぎ、前に進みやすくなる効果もあります。
最終的な目的は「高く・早く・揉めずに」売却することです。
状況に合った専門家とルートを選び、ムダな回り道を減らしましょう。
まとめ|共有名義は“時間が経つほど売れなくなる”
共有名義の不動産は、「いま売れる状態」だからこそ動けるのであって、
時間が経つほど売れない理由が増えていくという特徴があります。
相続・離婚・高齢化・ローン・感情対立など──共有名義が抱える問題は放置すると必ず悪化します。
- 最も高く売れるのは「全員合意で一括売却」
┗ 仲介で売るなら全体売却がベスト。ただし全員の意思統一が前提。 - 合意できない場合は「持分売却」という出口戦略もある
┗ 専門業者に持分のみ売却すれば、共有関係から“抜ける”ことが可能。 - 離婚・相続・ローン残債が絡む場合は早期行動が必須
┗ 放置すると「売れない→揉める→裁判化」へ発展するリスクが高い。
共有名義の不動産は、「いつ売るか」ではなく「売れるうちに動けるか」が勝負です。
すでに共有者同士の温度差がある場合は、感情で消耗する前に、専門家や共有持分買取業者へ相談するのが最短ルートです。
「もう少し様子を見る」は、共有名義では最も危険な判断になります。
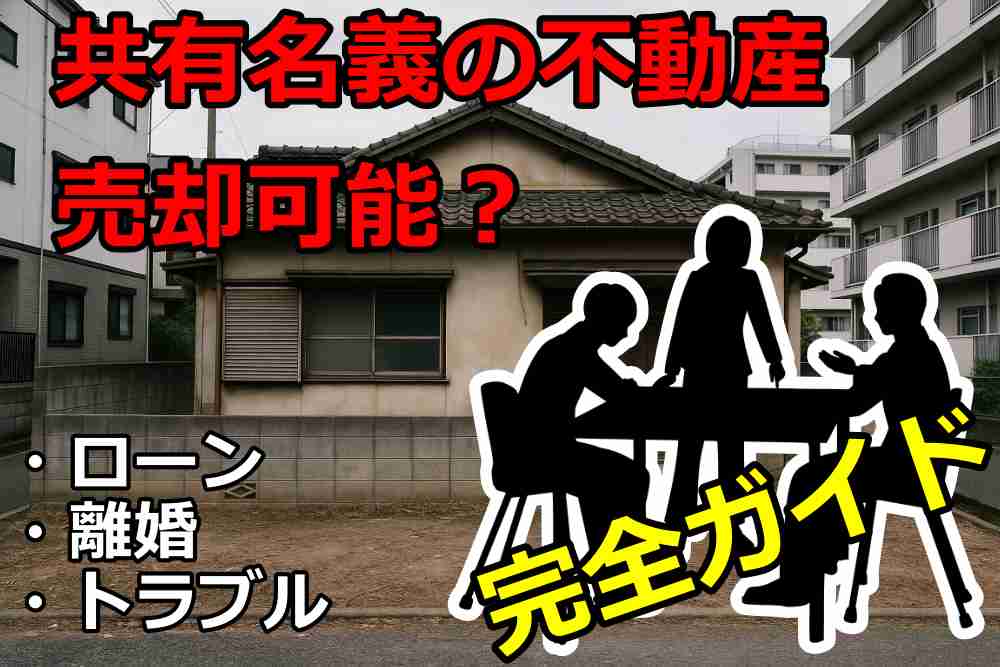


コメント