この記事では「再建築不可物件とは何か?」「なぜ建て替えできないのか?」「活用・売却するにはどうすればいいか?」がまとめてわかります。
固定資産税だけ払い続けて放置するか、それとも価値を少しでも高めて活用・売却するか──判断できる材料を整理しました。
専門用語をかみ砕いて解説しつつ、「リフォームできる範囲」「補助金は使えるのか?」「売却するならどこに頼むべきか」も具体的に紹介します。
再建築不可物件とは?まずは基本を正しく理解する

「再建築不可物件」という言葉を聞くと、なんとなく「古い家」「再利用できない土地」というイメージを持つ方も多いですが、実際には法律上の明確な理由で建て替えができない物件のことを指します。
「建て替えができない=価値がない」というわけではなく、条件次第では活用や売却も可能です。ただし、誤解されたまま放置してしまうと資産価値が大きく下がるリスクもあります。
まずは、再建築不可物件とは何か、その背景や発生理由を正しく知ることで、売却・活用の選択肢が広がります。
- 再建築不可物件の正式な定義
- 建築基準法と「接道義務」の関係
- 都市計画区域と再建築不可の発生背景
- 昭和25年・昭和43年以前の建物が多い理由
再建築不可になる主な理由
なぜ再建築ができないのかという問いには、法律・土地条件・法改正の影響という3つの視点で整理するとわかりやすくなります。
再建築不可になる原因は1つではなく、所有者の意思ではどうにもならないケースがほとんどです。そのため「知らなかった」「気づかなかった」は致命的な失敗につながります。
ここでは代表的な3つの理由を解説します。
理由①:接道義務を満たしていない
再建築不可の最も大きな理由は建築基準法に定められた「接道義務」を満たしていないことです。
これは、「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ建物を建てられない」というルールで、多くの再建築不可物件はこの条件をクリアしていません。
特に、昔ながらの路地や細い私道に面した住宅は、道路と認められず建て替え不可の状態に固定されてしまうことがあります。
理由②:既存不適格物件として扱われている
再建築不可物件の中には、建築当時は合法だったものの、その後の法改正により現在の基準に適合しなくなった「既存不適格物件」が含まれます。
たとえば、建築後に用途地域が変更された、道路認定が外れたなど、所有者の意思とは無関係に再建築不可となるケースも存在します。
このタイプの物件は、「古い=違法」という誤解をされやすく、誤った評価によって不当に安く扱われるリスクがあります。
理由③:区画整理・道路認定など法改正による影響
市街地整備や道路拡張などに伴い、かつて「道路」と認められていた部分が除外されるケースがあります。
この場合、所有者は何もしていなくても、ある日突然「再建築不可」に転落することがあるため注意が必要です。
そのため、再建築不可の判断は「見た目」ではできず、必ず役所・法務局での確認が欠かせません。
再建築不可物件はリフォームできる?できない?
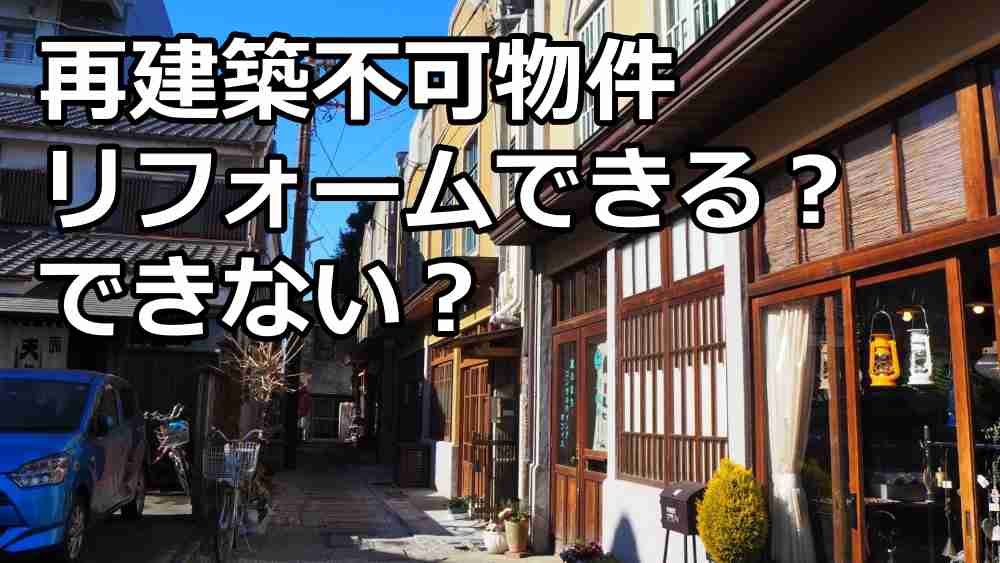
「建て替え不可=何もできない」と思われがちですが、実は再建築不可物件でもリフォームや改修が可能な場合があります。
ただし、どこまで工事できるか・どこからが制限されるかは、法律・物件の状態・自治体ごとの運用によって大きく異なります。
この章では、「可能な工事」「できない工事・注意点」「補助金との関係」という3つの視点で、再建築不可物件のリフォーム事情を整理します。
再建築不可でも可能なリフォーム工事
まずは「これはできる」工事の範囲を押さえておきましょう。所有者の方が「このくらいなら大丈夫かな?」と検討しやすい内容です。
- 建築確認申請が不要な改修工事 – 建物の躯体・構造を大きく変えず、10㎡以下の増改築や模様替えの範囲なら可能という説明があります。
- スケルトンリフォーム(構造を残して全面改修) – 柱や梁・床など主要構造部の1/2未満を残したまま改修するなら、再建築不可物件でも実施例があります。
- 耐震補強・配管更新・断熱工事などの修繕 – 建て替えはできなくとも、「住み続けるために必要な改修」は可能なケースが多いです。
再建築不可でできない工事・注意点
次に、所有者として誤った工事を行ってトラブルになる可能性がある範囲についてです。慎重に確認してください。
- 増築・増床・構造変更が制限される理由 – 建築確認申請が必要な工事(主要構造部を半分以上改修・増床等)は、再建築不可物件では認められないことが多いです。
- 自治体ごとの判断が違う点 – 同じ「再建築不可物件」であっても、道路扱いや防火地域かどうか、建物状態によって対応が異なります。地域の条例や役所への確認が不可欠です。
- 2025年4月の法改正に関する注意点 – 建築基準法改正により、大規模改修の要件が厳しくなる見込みで、再建築不可物件のリフォーム可能範囲が縮まる可能性があります。
再建築不可×補助金制度は使えるのか?
リフォームを検討するとき、補助金・助成金を活用したいと思われる方も多いでしょう。ただし再建築不可物件では条件がやや複雑です。
省エネ・耐震系補助金が対象になるケース
例えば、断熱改修・高効率給湯器の導入・耐震改修などは、全国で支援制度が用意されています。例えば「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」「長期優良住宅化リフォーム推進事業」などが該当例です。
補助金が使えない代表的なパターン
一方で、再建築不可物件が「建築確認申請を前提とした補助金制度」の対象となっていた場合、条件を満たせず申請できないケースがあります。建て替えや大規模構造変更が前提の制度では適用が難しいです。
リフォーム前に必ず確認すべき「申請条件」
補助金申請前には、契約書・図面・工事内容が対象要件を満たしているかを施工会社とともに確認することが重要です。また、同一工事部位で複数の制度申請ができるかどうかも自治体により異なります。
再建築不可物件を所有している人はどうするべきか?

再建築不可物件を所有していると、「このまま持ち続けて大丈夫?」「リフォームして住める?」「売るならいつ?」と迷う方が多いです。
結論として、再建築不可物件には4つの現実的な選択肢があります。
それぞれの選択肢にはメリット・デメリットがあるため、「放置する」のではなく、目的に合わせて判断することが大切です。
選択肢①:自分で住む・修繕して活用する
「建て替えはできないけど、今の建物を活かして住み続ける」という選択肢です。
再建築不可物件であっても、建築確認申請が不要な範囲のリフォームは可能なため、耐震補強・断熱工事・設備更新などの改善は行えます。
ただし、将来的に建物が劣化・倒壊した場合、再建築できず土地が「更地のまま活用できない状態」になるリスクがあります。
選択肢②:賃貸・民泊・倉庫などに活用する
「自分では住まないけど、収益物件として使いたい」というケースです。
再建築不可物件でも、戸建賃貸・倉庫貸し・貸し店舗・トランクルーム化などの活用例があります。
ただし、住宅ローンが利用できないため、買い手が投資家に限定される点や、建物維持コストが自己負担になる点に注意が必要です。
選択肢③:将来の売却を見据えて維持する
「今すぐ売る気はないが、いつかは手放すつもり」という場合は、現状維持ではなく“売れる状態を保つ”ことが重要です。
ポイントは以下の3つです:
- 建物を劣化させない最低限のメンテナンス
- 境界・権利関係を整理しておく(測量など)
- インフラの接続状況(水道・ガス・排水)を明確化
選択肢④:早期売却・専門業者への買取を検討する
「維持リスクを避けたい」「相続前に処分しておきたい」という場合は、早期売却が有効です。
特に再建築不可物件の場合、一般仲介よりも訳あり物件専門の買取業者のほうが成約が早いことが多く、現況のまま現金化できます。
所有しているだけで固定資産税・維持費がかかるため、「売るなら早いほど良い」という考え方も合理的です。
再建築不可物件を「早く・確実に」売りたい場合は、専門買取サービスの比較が参考になります。
>>> 訳あり物件に強い買取サービスの比較はこちら
対応スピード・価格傾向・向いているケースを分かりやすくまとめています。
再建築不可物件の売却方法と成功のポイント

再建築不可物件は確かに売却難易度が高いですが、「売れない」わけではありません。
むしろ、正しい売却方法を選べば想定より高く・早く売却できるケースも存在します。
ここでは「売れにくい理由」と「成功できる売却方法」をわかりやすく整理します。
再建築不可物件が売れにくい理由
- 住宅ローンが組めない=買主が限定される
- 銀行評価が低いため、購入者が現金買いか投資家に限定されやすい
- 建物の価値がほぼゼロと査定される
- 「将来解体すると建て替えできない」という出口リスクを買主が嫌う
売却時に選べる主な方法
再建築不可物件の売却方法は、大きく分けると3つあります。
その際のポイントとして、、その再建築物件をどう再利用するかのノウハウをしっかり持っているか否か、これが査定価格に影響します。
方法①:通常の不動産仲介で売却する
通常の仲介は、買主が「どうしてもこの物件がほしい」と判断した場合、もっとも高く売れる可能性がある方法です。
ただし、再建築不可というハードルがあるため、買主が見つかるまでに時間がかかり、売却期間が長期化しやすい点には注意が必要です。
また、「とりあえず高値で出して様子を見ましょう」という提案には要注意です。
相場から離れすぎた価格でスタートすると、問い合わせが減り、結果的に売却チャンスを逃すことがあります。
方法②:訳あり物件専門の不動産業者に売る
訳あり物件に特化した専門業者へ売却する方法は、最短で数日〜数週間ほどで現金化できるのが最大のメリットです。
「時間や手間をかけずに早く手放したい」という人に特に向いています。
専門業者は、再建築不可・共有名義・事故物件など、多様なケースを扱ってきた実績があります。
物件ごとの得意・不得意はあるものの、仲介よりも高値がつくケースも珍しくありません。
一般の仲介会社では難しい物件でも、スムーズに売却できる可能性があります。
方法③:隣地買取・接道改善による価値回復を狙う
隣地所有者に売却することで、相手側にとって「再建築可能化」のメリットが生まれ、高値売却できる場合があります。
仲介・専門買取・隣地売却の違いを理解したうえで、実際の買取サービスを比較するならこちら。
>>> 訳あり物件の買取サービス比較ガイド
買取価格の違い・得意分野・対応エリアなどを詳しく説明しています。
再建築不可物件の売却価格を上げる工夫
- 現況のまま売らず最低限の修繕を入れて“住める状態”にする
- 測量と境界確定でトラブルリスクを減らす(査定額アップ要因)
- インフラ設備(上下水道・ガス)とリフォーム履歴の開示で安心感を与える
まとめ|再建築不可物件は「知識」と「出口戦略」で価値が変わる
再建築不可物件は「使えない不動産」ではなく、正しく理解し正しく活用すれば、損せず活かせる不動産です。
一方で、知識がないまま放置すると、固定資産税などの維持費だけがかかり、価値は年々下がっていきます。
だからこそ、所有者が知っておくべきポイントを整理して振り返っておきましょう。
- 定義・理由・制約を正しく理解すればリスクは大幅に減らせる
- リフォームは可能だが、工事範囲と補助金制度の条件に注意が必要
- 売却は「仲介より買取業者の方が早い」ケースが多く、現金化しやすい
- 所有者が無知なまま放置するほど価値は確実に下がる(空き家・老朽化・税負担リスク)
再建築不可でも「どう活用するか・どう売るか」で未来は変わります。
どの売却方法が最適か判断するために、訳あり物件向けの買取サービス比較も確認しておくと安心です。
>>> 主要な買取サービスの違いと選び方を見る
再建築不可・共有名義・事故物件にも対応した業者を整理しています。
今のまま放置するか、維持しつつ活用するか、早期に売却して負担を減らすか──それを選べるのは所有者である「あなた」です。
もし判断に迷っているなら、専門業者への無料相談や査定だけでも一度受けておくのがおすすめです。
「知らないまま損する」を避け、「知って選べる立場」になりましょう。



コメント