「瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いがわからない」「期間は1年なの?10年なの?どっちが正しいの?」――
ここでは、そんな疑問をスッキリ解決します。
2020年の民法改正で仕組みが大きく変わったため、昔の知識のままだと“重大な勘違い”につながることもあります。
本記事では、旧制度と新制度の違い、責任期間の正しい考え方、住宅にだけ残る10年ルール、契約書での実務対策まで、初めての方でも理解できるように丁寧に整理しました。
「用語より、結局どう対応すればいいのか知りたい」という方こそ、ぜひ最後までお読みください。
瑕疵担保責任とは?わかりやすく基礎から解説(読み方・意味)

「瑕疵担保責任」という言葉を調べると、専門用語が多くて難しそう…と思った方もいるのではないでしょうか。
ですがご安心ください。この章では、まず「読み方」「意味」「どんなときに関係するのか」を、専門知識ゼロの方でも理解できるように整理していきます。
さらに、2020年4月に制度が大きく変わった背景もふまえ、基礎をしっかり押さえておくことで、後の章の理解もスムーズになります。
瑕疵担保責任の読み方と用語の基本
まずは、読み方と用語の意味から確認していきましょう。
法律用語としては少し難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえればカンタンです。
この段階でしっかり整理しておくことで、後で迷わず理解が進みます。
読み方:瑕疵=かし/担保=たんぽ/責任=せきにん
「瑕疵(かし)」とは、建物やモノにおける欠陥・不具合を示す法律用語です。
読み方を知っておくと会話や契約書の理解がスムーズになり、誤解を防ぐことができます。
意味:隠れた欠陥に対する売主・請負人の責任
「瑕疵担保責任」とは、売買や請負契約で引き渡された物に通常の注意では発見できない欠陥があった場合に、売主や施工側が負う責任のことです。
特に“隠れた瑕疵”がある場合でも責任を負うというのが重要なポイントです。
ただし、後ほど解説するように、2020年4月の民法改正により「契約不適合責任」という新制度へ移行しました。
不動産で想定される瑕疵のタイプ
瑕疵といっても、実は複数の種類に分類されます。
どれも売買トラブルでよく発生するポイントですので、事前に理解しておくことが大切です。
- 物理的瑕疵:雨漏り・シロアリ・耐震不足など
- 法的瑕疵:用途制限違反・再建築不可など
- 心理的瑕疵:事故・孤独死・周知の事案
- 環境的瑕疵:悪臭・騒音・地盤沈下など
瑕疵担保責任が問題になる典型場面
では実際に「瑕疵担保責任」が争点になるのはどんな場合でしょうか?
ここでは不動産取引における具体的なトラブル例から、イメージしやすく解説していきます。
「そういう場面で問題になるんだ」と理解しておくことで、予防や対策にもつながります。
売買契約:引渡し後に欠陥が判明するケース
中古住宅を購入後に雨漏りが発覚した…といった場合、買主は売主へ修補や損害賠償を求められる場合があります。
ただし、契約書に免責条項がある場合は状況が変わるため注意が必要です。
請負契約:完成物の品質・性能が契約に届かない
注文住宅やリフォーム工事などで「依頼した内容と違う」「基準に達していない」といった場合も、瑕疵担保責任の対象になります。
トラブルの多くは“完成物の品質・性能の認識のズレ”が原因です。
免責合意・現状有姿の記載がある場合
契約書に「現状渡し」「瑕疵担保責任免除」などの記載がある場合、売主側が責任を負わなくてもよいケースがあります。
ただし「免責だから絶対に責任が問われない」とは限らないため、内容確認は必須です。
特に宅建業者が売主の場合、法律上の制限がある点も押さえておきましょう。
瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い(改正のポイント)

2020年4月の民法改正によって、従来の「瑕疵担保責任」は、制度的に整理されて「契約不適合責任」という枠組みに変わりました。
この変更は、単なる用語の入れ替えではなく、買主・売主双方に関わる責任範囲・請求手段・期間の考え方が大きく見直されており、実務にも影響を与えています。
この章では、まず「なぜ改正されたのか」という背景を整理し、その後に旧制度・新制度の違いをわかりやすく比較します。最後に誤解しやすいポイントも確認しておきましょう。
なぜ改正されたのか(背景)
まず、制度が改正されるに至った背景を理解すると、各変更点の意味がぐっと明確になります。
法律の言葉だけでは分かりづらい「改正の目的」を、実務や取引の視点から掘り下げます。
この背景を理解することで、新制度を使いこなすための視点も養えます。
「隠れた瑕疵」の線引きが実務で難しかった
旧制度では、売主が引き渡した物件に「隠れた瑕疵」があった場合に責任を負うという考え方が中心でした。
しかし、この「隠れた」という条件を巡って「知っていた/知らなかった」「見えた/見えなかった」といった争いが頻繁に発生し、契約の安定を妨げる原因となっていました。
契約内容との適合性へ視点を転換
そこで改正後は、物件そのものが隠れていたかどうかではなく、引き渡された物件が「契約で定めた種類・品質・数量に適合しているか」を基準とする制度に変わりました。
このように基準を契約内容へと切り替えたことで、売主・買主双方にとって明確性が高まり、実務での混乱を減らすことが目的でした。
違いをわかりやすく比較
以下に、旧制度と新制度の間で代表的な変更点を整理しました。
違いを把握することで、契約書チェックやトラブル防止の準備がぐっとラクになります。
対象の違い:旧=隠れた瑕疵 / 新=契約内容への不適合
旧制度では、「隠れた瑕疵」であることが発生要件でした。つまり、買主が通常の注意をしていて気づけなかった欠陥である必要がありました。
新制度では、物件が契約で定められた内容に合っているかどうかを問題にするので、買主が欠陥を知っていた/知らなかったという線引きは中心ではなくなりました。
救済手段の拡充:追完請求・代金減額請求が明文化
- 追完請求(修補・代替物・不足分引渡)
- 代金減額請求
- 損害賠償・解除(要件を満たす場合)
旧制度では、主に「契約解除」または「損害賠償請求」に限られていましたが、改正後の契約不適合責任では、上記のような多様な救済手段が明文化されています。
期間の考え方:旧=1年の権利期間/新=通知を軸とする運用
旧制度では、「瑕疵を知った時から1年以内に請求しなければならない」という厳格なルールがありました。
新制度においては、買主が契約内容に適合しない状態を知った時から1年以内に売主へ通知すれば、追完や代金減額などの請求を後から行えるという運用に変わっています。
「買主が知っていた」扱いの変化
旧制度では、買主が欠陥を知っていた・または通常の注意で気づけたという場合、売主の責任追及が制限されるケースが多くありました。 :contentReference[oaicite:7]{index=7}
新制度では、買主が知っていた/知っていなかったにかかわらず、契約内容に合っていないと判断された場合に責任を問うという考え方が定着しつつあります。つまり、契約の合意内容がより重視されるようになりました。
誤解しやすいポイントの整理
最後に、実務で見落とされがちな“誤解ポイント”をまとめます。事前に理解しておくことで、トラブルになるリスクを減らせます。
少しでも「何かおかしいかも」と思ったら、このチェックポイントを思い出してください。
「隠れていれば責任」はもう古い
「隠れた瑕疵でないと責任を問えない」という考え方は、旧制度の名残です。新制度では、契約で定められた仕様との適合性が判断基準となります。
特定物・不特定物の区別に依存しない
旧制度では「特定物(個別に指定された物)であるかどうか」が論点となるケースがありましたが、改正後はその区別に関係なく、契約内容に対する適合性がベースになります。
旧用語のままの契約書は要アップデート
契約書や約款が旧制度のまま(例えば「瑕疵担保責任」と記載)である場合、実務上の解釈や条件にズレを生む恐れがあります。新制度に即した条項・運用に改訂しておくことが重要です。
瑕疵担保責任期間と契約不適合責任の期間(実務の肝)

不動産売買や請負契約でとても気になるのが、責任を追及できる「期間」です。
旧制度の「瑕疵担保責任」と、現行制度の「契約不適合責任」では、期間の考え方が明確に異なります。
特に住宅取引では、〈通常の責任期間〉に加えて、〈住宅特例〉の10年ルールもありますので、この章でしっかり整理しておきましょう。
旧制度(瑕疵担保責任)の期間
旧制度の瑕疵担保責任は「引渡し後1年以内に権利行使しなければならない」という期間制限が特徴でした。
さらに新築住宅には品確法による10年ルールも存在。
制度改正前の取引では今も適用されるため、現行制度との違いを正確に把握することが重要です。
原則:引渡し後1年以内の権利行使
旧民法では、買主が物件の瑕疵を知ってから、または引渡し後一定期間内に請求・通知をしなければ、売主に対して責任を追及することが原則としてできませんでした。
多くの解説では「引渡しから1年以内に行動を起こす必要があった」と整理されています。
住宅の特例:品確法による10年
一方、〈新築住宅〉に関しては、〈住宅の品質確保の促進等に関する法律〉(品確法)によって、売主は構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に対して、引渡しから10年間の責任を負うことが義務付けられています。
この期間は、契約書で短くすることができず、強制的な規定ですので、非常に重要なポイントです。
新制度(契約不適合責任)の期間
続いて、2020年4月の民法改正以降に適用される契約不適合責任の期間ルールを見ていきましょう。
旧制度の「1年ルール」とは異なり、新制度では〈不適合を知った時から一定期間内の通知〉が必須。
期間を誤ると請求権を失うため、正しい理解が欠かせません。
基本は「通知期間」を守ること
改正民法(第566条、第637条等)では、買主が契約内容との不適合を知ったときから1年以内に売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除といった権利を行使できないルールが定められています。
つまり「知ったらすぐ通知」が肝であり、通知を怠ると権利が消えてしまう可能性があります。
特約の可否:免責・短縮の扱い
一般契約ではこの通知期間が基準となりますが、契約書で特約を結ぶことにより、期間を短縮・免除する方向も可能です。
ただし、〈売主が宅建業者〉である場合は、〈宅地建物取引業法〉等の規制によって、買主に著しく不利な特約は無効になる可能性があります。
契約を交わす際には、このような「通知期間・特約」の条項をよく確認しましょう。
品確法(住宅の品質確保法)の地位
住宅取引では、民法の制度変更と並び、品確法による特例の理解も欠かせません。
品確法は民法改正後も独立して効力を持ち、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について10年間の責任を義務化しています。
契約不適合責任とは別枠で適用されるため、住宅取引では両制度の併存を理解しておくことが重要です。
新築住宅は改正後も「10年」が存続
改正民法によって契約不適合責任の制度が整備されたものの、新築住宅に対する義務として、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に関し、売主には引渡しから10年間の責任が継続しています。
対象部位の範囲と実務の留意点
対象部位とは「住宅の構造耐力上主要な部分」「雨水浸入を防止する部分」です。
契約時点でその範囲を明確にし、図面・写真・仕様書など記録を残しておくことが、後のトラブル防止につながります。
実務での防衛術:契約書・特約・免責の見直し

不動産の売買・請負でトラブルを未然に防ぐには、単に「法律を知っている」だけでは不十分です。
契約書の書きぶりや特約の内容、免責条項、さらに社内のオペレーションまで整備しておくことが、実務上の肝(きも)となります。
この章では、契約書で必ず整えるべき項目、免責条項の扱いや限界、トラブル時の基本的な動き方を、わかりやすく整理します。
契約書で必ず整えるべき要素
契約書を作成する際、曖昧な記載や不十分な条項が後のトラブルの原因になることが多いです。
ここでは、契約書に記載しておきたい重要項目を具体的に見ていきましょう。
契約内容の明確化:種類・品質・数量・性能
契約書には、物件・完成品がどのような「種類」「品質」「数量」「性能」を満たすべきかを、明確に記載しましょう。
たとえば「耐震基準適合」「雨水浸入を防止」「外壁材グレード〇〇」というような具合に、できるだけ具体的に仕様を記述することで、契約内容との適合性を後から判断しやすくなります。
容認事項・現状有姿の明記
売主側が知っている劣化・不具合・築年数の経過などを、買主が了承する形で「容認事項」「現状有姿」として契約書に明記しておくことが重要です。
このような記載があれば、買主が「知らなかった」と主張するリスクを減らせますし、実務トラブルの抑止にもつながります。
通知・連絡フローの明文化
不適合・瑕疵が発覚した場合、買主が売主に通知する期限・方法(書面・メール・電話)・連絡先を契約書に定めておくと安心です。
トラブル発生時に「いつ誰にどう連絡したか」が争点になることが多いため、通知フローを条項化しておくことで、スムーズな対応づくりとなります。
免責条項の扱いと限界
売主側としては「免責にしたい」「売った後のリスクを抑えたい」という意向もありますが、免責条項には法律的な制限があります。
ここでは、売主が個人か業者かによって異なる制限・注意点を整理します。
個人売主と業者売主で異なる裁量
売主が個人の場合、契約自由の原則から比較的広く免責・責任の制限が認められます。
しかし、売主が〈業者〉(特に〈宅地建物取引業者〉)で買主が〈個人〉の場合には、法律(〈宅地建物取引業法〉)により免責・権利制限の特約が無効になる可能性があります。
任意売却・競売物件での実務
任意売却や競売物件では「現状有姿・瑕疵担保責任免責」という条件付きで販売されるケースが多いです。
買主側としては、物件の調査(インスペクション/履歴確認)をしっかり実施し、契約書の免責条項を理解したうえで承諾するプロセスが非常に重要です。
トラブル時の基本動線
万一、契約不適合・瑕疵が発覚した場合に取るべき基本的な流れを整理します。
事前対応をしておくことで、迅速かつ適切な処理が可能になります。
①事実確認 → ②通知 → ③協議 → ④手当
まずは、どのような不適合・欠陥が発生しているかを確認します。
次に、契約書の通知条項に従って売主へ連絡・書面提出し、協議に入ります。
協議が整わない場合には、履行の追完・代金減額・損害賠償・解除など、契約・法律に基づく手当を講じます。
選択肢の整理:追完/減額/損害賠償/解除
対応手段としては以下のような選択肢があります。
- 履行の追完(欠陥の修補・代替物の引渡し)
- 代金減額請求
- 損害賠償請求
- 契約解除
どの選択が最適かは、欠陥の程度・対応コスト・履行可能性・通知期間の経過などを考慮して判断します。
FAQ|瑕疵担保責任・契約不適合責任でよくある質問

「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違い、2020年改正のポイント、責任期間や通知期限、免責特約の扱いなど、現場で迷いやすい疑問に端的に答えます。
実務で失敗しない要点をサクッと確認しましょう。
Q1. 「瑕疵担保責任」とは今も使う言い方ですか?
A:実務では通称として残りますが、現行民法は「契約不適合責任」が正式用語です。
Q2. 改正はいつから?過去の契約はどうなりますか?
A:2020年4月1日以降に成立した契約は原則として「契約不適合責任」が適用されます。それ以前の契約では、当時の条項・制度(瑕疵担保責任)がベースとなります。
Q3. 瑕疵担保責任期間は1年固定ですか?
A:旧制度(瑕疵担保責任)では、原則として引渡しから1年以内に請求を行う必要があるという考え方が基本でした。新制度(契約不適合責任)では、〈不適合を知った時から一定期間内に通知〉という運用が重要となっており、1年という数字が目安となることが多いですが、必ず固定ではありません。
Q4. 新築住宅の10年は今も有効ですか?
A:はい。〈住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)〉により、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」について、引渡しから10年間の責任が継続して規定されています。特約で短くすることはできません。
Q5. 免責特約は自由に設定できますか?
A:当事者間で合意すれば、免責特約を設けることは可能です。ただし、売主が〈宅地建物取引業者〉である場合には、免責や期間短縮を一方的に設けることが法令によって制限されるケースがあります。
Q6. 心理的瑕疵や環境的瑕疵も責任対象ですか?
A:はい。心理的・環境的な瑕疵も、契約書で定めた仕様・説明義務・容認事項などとの関係で対象になりうるもので、事前に説明があったか、買主が了承していたかがポイントとなります。
Q7. 契約書はどこを見直せばよいですか?
A:契約書を見直す際には、以下の4点を重点的にチェックしてください。仕様の明確化/容認事項の明記/通知方法・期限/免責の範囲と限界です。
まとめ|「改正」を理解し、期間と通知でミスらない
ここまで解説してきたとおり、2020年4月の民法改正により「瑕疵担保責任」は実務上「契約不適合責任」へと再定義され、考え方・責任範囲・救済手段が大きく変わりました。
しかし、名称が変わっただけではなく、実務対応そのものに影響する改正であることが最も重要なポイントです。
特に「期間」と「通知」の扱いを誤ると、請求できるはずの権利を失う可能性があるため、正確な理解と運用が不可欠です。
押さえるべき3点
最後に、実務で失敗しないための重要ポイントを3つに整理します。
● ① 用語より中身:適合性と救済手段の拡充が本質
改正の本質は名前の変更ではなく、「隠れた瑕疵」から「契約内容との適合性」へ基準が変わったことです。
さらに、追完請求・代金減額請求などの救済手段が明文化され、買主側の選択肢が増えました。
● ② 期間の理解:旧=1年の権利期間/新=通知期間が肝
旧制度では「発見から1年以内の権利行使」が原則でしたが、新制度では『不適合を知った時から一定期間内に通知』することが必須となりました。
通知を忘れると請求ができなくなるため、実務では「気づいたら即通知」が鉄則です。
● ③ 実務対応:契約書の精緻化と社内オペの整備
制度理解と同じくらい重要なのが、契約書の適正化と社内フローの整備です。
仕様の明確化、容認事項の記載、通知方法の条文化、免責の限界確認などが欠かせません。
つまり、「瑕疵担保責任 改正」を正しく理解し、「瑕疵担保責任期間」と通知の扱いを誤らないことが、トラブル防止と迅速解決の近道です。
実務に携わる方は、ぜひこの機会に契約書・特約・運用体制を見直してみてください。
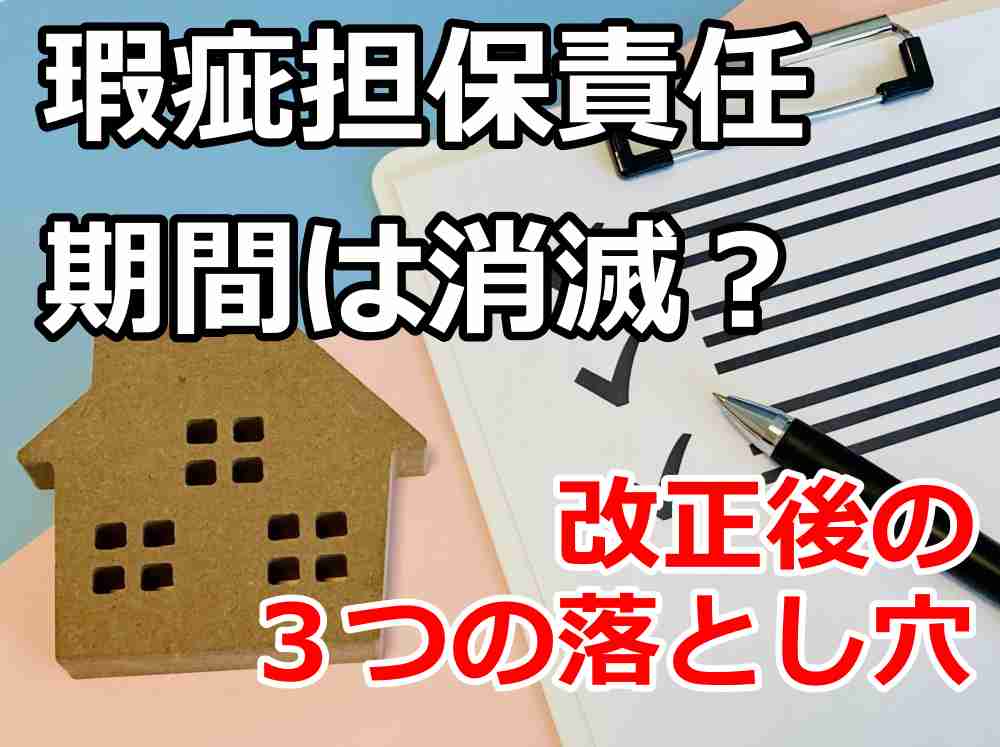


コメント