「再建築不可物件って売れるの?リフォームや建替えはできるの?」──
ここでは、そんな疑問を持つ方に向けて再建築不可物件の基礎知識から相場、リフォームや建替えの可否、売却・買取の方法までを分かりやすく解説します。
固定資産税の負担やローンが組めないリスクなど、不安を抱えたまま放置していると損をしてしまう可能性もあります。
「自分の物件はどう活用すべきか」を判断するヒントが得られる内容になっていますので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
再建築不可物件とは?基本定義と特徴

「再建築不可物件」という言葉を聞いて、不安を感じる方は少なくありません。
相続や購入を検討している家が「再建築不可」と言われると、将来どうなるのか心配になりますよね。
ここでは、まず基本的な定義や特徴を整理し、なぜそのような物件が存在するのかを分かりやすく解説します。
再建築不可物件の定義
再建築不可物件とは、建物を一度解体して更地にすると新しい建物を建てられない土地や家のことを指します。
これは単なる不便さではなく、法律で定められたルールに基づくものです。
つまり、住み続けることはできますが「建て替えができない」という制約を持つ物件なのです。
建築基準法における接道義務
建築基準法では、敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ建築不可とされています。
これを「接道義務」と呼び、再建築不可物件の多くはこの要件を満たしていません。
特に狭い道路や私道しか面していない土地は要注意です。
既存不適格物件とは何か
以前は合法だった建物でも、法律改正によって今は新築できない土地に変わってしまう場合があります。
これを「既存不適格物件」と呼び、再建築不可の代表的な事例です。
つまり「今は住めるが、建て替え時に制限される」というリスクを抱えています。
再建築不可になる主な理由
再建築不可物件となる背景にはいくつかの理由があります。
ここでは代表的な要因を2つに分けて解説します。
「なぜ建て替えられないのか?」を理解することで、リスクを正しく把握できるようになります。
接道要件を満たさないケース
最も多いのが接道要件を満たさない土地です。
間口が狭い、道路に面していないなどの理由で再建築不可になります。
この場合、建物を壊した時点で新しい建築確認が下りません。
都市計画・法改正によるケース
都市計画や道路拡幅などに伴い、以前は建築可能だった土地が後から再建築不可に指定されることもあります。
これは所有者の意思に関係なく、法改正によって決まってしまう点が特徴です。
「いつの間にか制限がかかっていた」というケースも少なくありません。
再建築不可物件の具体的な事例
抽象的に説明されても分かりづらいので、実際によくあるケースを紹介します。
これらは特に都市部や古い住宅地で見られるパターンです。
自分の所有地や相続予定の土地が当てはまっていないか、確認する参考になります。
狭小地に多いケース
間口が狭く、細い道にしか接していない土地は再建築不可になる典型例です。
都市部の古い住宅街に多く、土地は便利でも建て替えできないという大きな制約を抱えています。
住み続けることは可能ですが、資産価値は大きく下がります。
路地状敷地(旗竿地)のケース
細い通路の奥に建物がある旗竿地も再建築不可になりやすい土地です。
通路部分が接道条件を満たさず、建て替え時に許可が下りません。
「便利な場所だから」と安易に購入すると、後で後悔するリスクが高いエリアです。
\ 業界トップクラスの実績!今すぐ価値を確認 /
>>> 再建築不可物件の無料査定はこちら![]()
/ 最短3分で相場がわかり、損を防げます \
再建築不可物件はどうなる?所有リスクと放置コスト

「再建築不可」と言われると、まず気になるのは「このまま所有して大丈夫なのか?」という点ですよね。
実際に所有してみると、資産価値の低下や税金の負担、そして売れにくさなど、放置することでリスクが年々大きくなっていきます。
ここでは、再建築不可物件を持ち続けることで直面する代表的なリスクを整理して解説します。
資産価値の低下
再建築不可物件の最大の特徴は、再建築可能な物件に比べて資産価値が大幅に低いことです。
建て替えができないという制約は、不動産としての魅力を大きく下げてしまいます。
そのため、売却しようと思っても、希望価格ではなかなか買い手が見つからないのが現実です。
再建築可物件との価格差
一般的な目安として、再建築可の5〜7割にとどまる事例が多い(立地・建物状態・隣地条件で上下)ようです。
便利な場所にあっても、建て替えができない制約があるだけでここまで下がってしまうのです。
つまり、資産としての将来性は大きく制限されてしまいます。
買い手が限定される理由
再建築不可物件は、購入を検討する人が限られています。
なぜなら「建て替えられない土地」にわざわざ投資する人は少ないからです。
そのため、購入するのは現金で買える投資家や、隣地を持つ人など、特殊な条件を持った層に絞られてしまいます。
税金・維持コストの増加
再建築不可物件は売却が難しいため、長期間所有し続けることになりがちです。
その間も税金や管理費はかかり続け、放置しているだけでコストが増えていきます。
「使わないのに負担だけが続く」というのは所有者にとって大きな悩みです。
固定資産税の扱い
建物がある間は住宅用地の特例で税負担が軽減されています。
しかし、もし建物を壊して更地にしてしまうと住宅用地特例が外れ手島います。
結果、固定資産税の課税標準は最大6倍(都市計画税は最大3倍)に増える可能性があります。
「壊すかどうか」で負担が大きく変わるのが再建築不可物件の特徴です。
老朽化による修繕費用
再建築不可物件を放置していると、建物が老朽化して修繕費用がかさみます。
雨漏りやシロアリ被害などを放置すると、周囲への危険にもつながり行政から指導を受けるケースもあります。
結果的に「使えない家に修繕費を払い続ける」という悪循環になりやすいのです。
市場での売れにくさ
再建築不可物件は、資産価値が低いだけでなく「売れにくい」という問題も抱えています。
売りに出しても買い手が限られているため、長期間売れ残るケースが多いのです。
ここでは、その理由を具体的に見ていきましょう。
ローンが組めないため現金購入者に限定
再建築不可のままでは住宅ローンは極めて困難です(例外:43条許可で建築可能と認められる場合など)
そのため、買えるのは現金を持つ人だけに限定されます。
これは売却のハードルを大きく上げる要因です。
売却期間が長期化するリスク
買い手が少ないため、売却期間は通常の物件より長期化しやすいです。
売れるまで数ヶ月〜1年以上かかるケースも珍しくありません。
「早く手放したい」と思っても、思うように進まないのが現実です。
\ 面倒ごとから解放! /
>>> 再建築不可物件の査定はこちら![]()
/ 現状のまま査定OK!業界トップクラスの実績\
再建築不可物件の調べ方

「この家や土地は再建築できるの?」と疑問に思ったとき、正しい調べ方を知っておくことはとても大切です。
誤った判断をしてしまうと、売却や相続で思わぬトラブルにつながることもあります。
ここでは、自分で確認する方法から、自治体や専門家を頼る方法まで順を追って解説します。
自分で確認する方法
まずは自分でできる範囲から調べてみましょう。
簡単なチェックだけでも「再建築不可の可能性があるかどうか」を見極められることがあります。
ただし自己判断だけで結論を出すのは危険なので、参考として活用してください。
接道義務の測り方
建築基準法では、土地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが必要です。
物件が面している道路の幅を実際に測ることで、基準を満たしているかある程度確認できます。
ただし「見た目の道路幅」と「法的に認められている道路幅」は異なる場合があるので注意が必要です。
地図や登記簿のチェック
公図や登記簿謄本を確認することで、その土地の境界や道路との関係が分かります。
特に接道部分の幅や道路の種別は、再建築の可否を判断する重要な材料です。
市区町村のホームページでも公図や都市計画図が閲覧できる場合があります。
自治体・法務局で確認する方法
自分での確認に不安がある場合は、自治体や法務局に問い合わせて確認するのがおすすめです。
専門部署で確認することで、より正確に「再建築可か不可か」が判断できます。
ここでは代表的な確認先を紹介します。
建築指導課での相談
市区町村の建築指導課では、接道要件を満たしているかどうかを相談できます。
図面や登記簿を持参すれば、専門の担当者が具体的にアドバイスしてくれます。
「無料で確認できる」ことが多いので、まずは気軽に問い合わせるのが賢い方法です。
道路台帳での確認
市区町村が管理する道路台帳を確認することで、その道路が建築基準法上の道路に該当するかが分かります。
たとえ舗装されていても、法的に道路と認められていなければ接道義務を満たせません。
「生活道路だから大丈夫」と思い込むのは危険です。
専門家に依頼する方法
最も確実なのは、不動産の専門家に依頼して調べてもらう方法です。
自分で調べるよりも精度が高く、売却や相続を考えている場合は早めに相談することをおすすめします。
ここでは代表的な依頼先を2つ紹介します。
不動産会社に調査を依頼
不動産会社では、売却査定の一環として再建築可否の調査をしてくれることがあります。
その土地の相場感や売却可能性も合わせて確認できるため、実用的な方法です。
「売却を前提に調べたい」という方には最適な選択肢です。
弁護士・司法書士への相談
権利関係が複雑な場合や、相続が絡むケースでは弁護士や司法書士に相談するのが安心です。
法律の専門家に確認してもらうことで、後々のトラブルを未然に防げます。
特に共有名義の土地は早めの相談がトラブル回避につながります。
\ 自己判断はもう卒業 /
>>> 再建築不可物件の無料査定はこちら![]()
/ 専門家チェックで安心!ワンストップで 解決に \
再建築不可物件の相場を知る
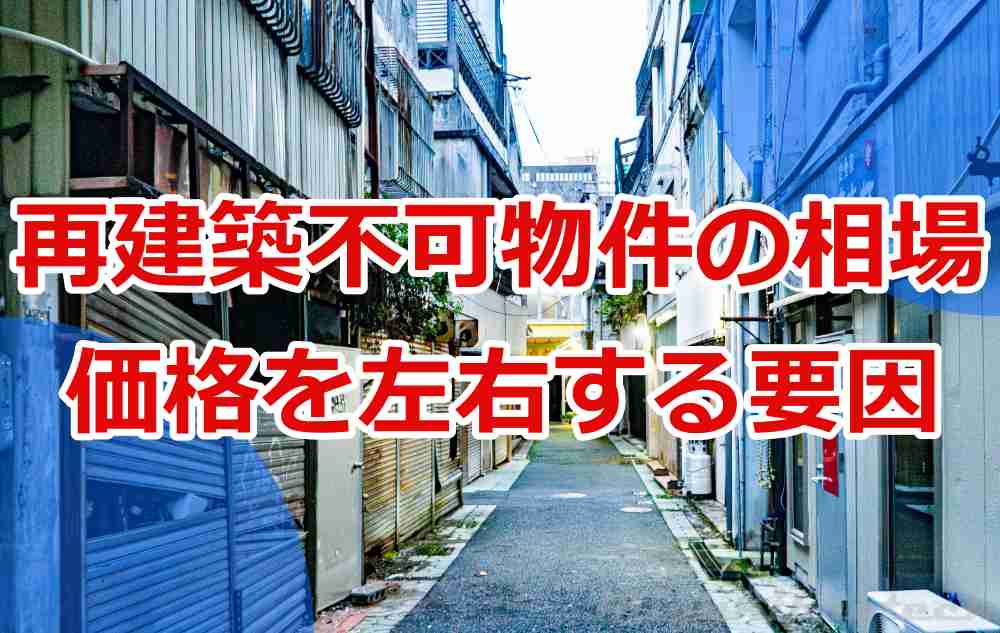
「再建築不可物件はいくらくらいで売れるのか?」これは多くの所有者や相続人が抱える疑問です。
一般の不動産と比べると資産価値が大きく下がるのが特徴ですが、その幅や理由を正しく理解することが重要です。
ここでは一般的な価格水準から、価格を決める要因、さらに東京など都市部での実情まで詳しく見ていきます。
一般的な価格水準
再建築不可物件は、通常の再建築可能な物件と比べて明らかに価格が低く設定されます。
その背景には「建て替えができない」という制約があり、将来的な資産価値の見通しが悪いことが理由です。
ここではその価格差の具体的な理由を整理します。
再建築可の5〜7割に下がる理由
一般的に、再建築不可物件の価格は再建築可物件の5〜7割程度に下がります。
理由は明確で、銀行ローンが使えない・買い手が限定される・建て替えができないといった資産価値を下げる要因が重なるためです。
つまり、立地が良くても制約があるだけで価格は大きく下がってしまうのです。
地域ごとの相場感
再建築不可物件の価格は、地域によって差があります。
地方では需要が少なく、価格がさらに低くなる傾向があります。
一方、都市部では利便性が高いため、制約があっても買い手がつくケースもあります。
価格を左右する要因
同じ「再建築不可物件」でも、価格には幅があります。
その差を生むのは、立地・建物の状態・隣地との関係といった要素です。
ここでは代表的な3つの要因を解説します。
立地条件
再建築不可物件でも、駅近や商業地域など立地条件が良い場所では需要があります。
便利な場所であれば、制約があっても住みたい・投資したいという人が現れるためです。
逆に立地が悪い場合は、制約が重なってさらに価格が下がります。
建物の老朽度
建物が老朽化している場合、リフォームや修繕に費用がかかるため価格は下がります。
逆に、しっかり管理されている建物は価値を保ちやすいです。
築年数だけでなく、メンテナンス状況も価格を大きく左右します。
隣地との関係
隣地所有者が購入を希望するケースでは、価格が上がることもあります。
接道条件を満たせる可能性があるため、隣地にとっては価値が高まるからです。
このケースでは通常より有利な価格で売却できる可能性があります。
東京など都市部での実情
東京など都市部では、再建築不可物件が意外と多く存在しています。
特に古い住宅地や細い道路が多いエリアでは再建築不可の割合が高い傾向にあります。
ここでは都市部での特徴を2つ解説します。
再建築不可物件が多いエリア
都心部の木造密集地域で接道不良が多く、再建築不可が一定数存在(一部業界推計では“23区で約5%”との指摘もあるが、公的に確定した比率ではない)。」します。
※参考:都市整備局
狭い道路や路地が多い地域は、接道義務を満たしていないケースが多いためです。
墨田区・台東区・足立区などは特に該当物件が多いエリアとして知られています。
投資対象としての需要
都市部では、再建築不可物件であっても投資対象として買われることがあります。
賃貸需要が高いエリアでは、建て替えできなくてもリフォームして貸し出すことで収益化できるためです。
「住む目的」よりも「投資目的」での購入が多いのが都市部の特徴です。
\実績が多い業者で損せず売る第一歩! /
>>> 再建築不可物件の価値を確認![]()
/ 相場以上で売れるケースもあります \
再建築不可物件とリフォーム

「再建築不可物件は建て替えができないから、もう使えないのでは?」と思う方も多いかもしれません。
しかし実際には、建物を壊さずに残すことでリフォームや修繕は可能です。
ここでは、再建築不可物件でできるリフォームの範囲や価値を高める方法、注意点を整理して解説します。
できるリフォームの範囲
再建築不可物件は「建て替え」ができないだけであり、建物を壊さずに行うリフォームは認められています。
老朽化して使いづらくなった建物でも、工夫次第で快適に活用できるのです。
代表的なリフォームの種類を見ていきましょう。
内装・設備のリフォーム
キッチンやお風呂、トイレなどの水回り設備は自由にリフォーム可能です。
壁紙の張り替えや床の張り替えなど、生活空間を快適にする工事は問題なく行えます。
「古い家だから」と諦めるのではなく、内装を刷新することで大きく住み心地が変わります。
耐震補強工事
再建築不可物件は古い建物が多く、耐震性に不安があるケースが目立ちます。
そのため、柱や基礎部分を補強する耐震補強工事は有効な手段です。
補強を行うことで安全性を高め、資産価値の維持にもつながります。
リフォームで価値を高める方法
再建築不可物件でも、リフォーム次第で価値を上げられます。
そのまま住むのはもちろん、賃貸や投資として活用することも可能です。
ここでは代表的な活用例を紹介します。
賃貸用に活用するケース
内装を整えれば、再建築不可物件でも賃貸物件として貸し出すことができます。
立地が良ければ入居希望者は見つかりやすく、安定した収入源になることもあります。
「建て替えられない=無価値」ではなく「収益化できる資産」に変えられる可能性があります。
リノベーション投資としての活用
フルリノベーションしておしゃれな内装にすれば、投資用としての需要も見込めます。
特に都市部では「古民家風」「レトロな雰囲気」を活かした賃貸ニーズが高まっています。
低価格で仕入れて高利回りを狙えるのが、再建築不可物件を投資で使うメリットです。
リフォーム時の注意点
一方で、再建築不可物件のリフォームには注意すべき点もあります。
知らずに工事を進めると「違法建築」とされるリスクがあるため、事前に確認することが大切です。
ここでは代表的な注意点を解説します。
増築ができないケース
建物を大きくする増築工事は基本的に認められません。
建物の面積を広げると、新たに建築確認が必要になり、その時点で再建築不可と判断されてしまうからです。
リフォームする場合は「現状の建物を活かす」工事にとどめる必要があります。
建築確認申請が必要になるケース
耐震補強や間取り変更など、構造に影響を与える工事を行う場合は建築確認申請が必要です。
申請が必要な工事を無許可で進めると違法となり、後々大きなトラブルにつながります。
工事前には必ず専門家に確認を依頼することをおすすめします。
\ 再建築不可でも活かせる! /
>>> 再建築不可物件の無料査定はこちら![]()
/ リフォームか売却か相談して安心の一歩へ \
再建築不可物件と建て替え

「古くなったから建て替えたい」と思っても、再建築不可物件では簡単に実現できません。
実は「再建築不可」という名称の通り、法律的に新しい建物を建てることが制限されているのです。
しかし、条件次第では例外的に建て替えが可能になるケースもあります。ここではその理由と可能性を整理して解説します。
なぜ建て替えができないのか
再建築不可物件は「建物を建て替えることができない土地」として扱われます。
その背景には、建築基準法による厳しいルールが関係しています。
ここでは代表的な理由を2つ紹介します。
接道義務を満たさないため
建築基準法では、敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。
この条件を満たさない土地は建築不可とされるため、建て替えも認められません。
細い路地や行き止まりの土地は、この接道義務を満たせないため再建築不可になることが多いです。
建築確認が下りない仕組み
新しく建物を建てる際には、役所の建築確認申請が必要です。
接道義務を満たしていない土地では、この建築確認が下りないため建て替えができません。
つまり、制度上「建てたくても許可が下りない」という仕組みになっています。
例外的に建て替えできるケース
一見すると完全に不可能に思える建て替えですが、例外的に可能になるケースもあります。
ただし多くの場合、隣地の協力や追加の手続きが必要です。
ここでは代表的な2つの方法を紹介します。
隣地を買い足す方法
隣接する土地を購入し、接道部分を広げることで接道義務を満たせる場合があります。
この方法が成功すれば、再建築可能な土地へと変えることができます。
費用はかかりますが、資産価値を大きく回復できる可能性があります。
セットバックで道路要件を満たす方法
敷地の一部を道路として提供するセットバックにより、道路幅を広げる方法もあります。
これによって法的に「道路」として認められ、建て替えが可能になるケースがあります。
ただし、敷地が狭くなってしまう点には注意が必要です。
道路の種別確認=道路台帳・建築指導課 東京都の場合: 都市整備局
建て替えにかかる手続きと費用
再建築不可物件を建て替える場合、通常の建築以上に手続きや費用がかかります。
そのため、事前に流れとコストを把握しておくことが大切です。
ここでは代表的な注意点を紹介します。
行政との協議が必要な場合
セットバックや接道条件の緩和を受けるには、行政との協議や許可が必要です。
場合によっては都市計画課や建築指導課と何度も調整する必要があります。
この段階で時間がかかることを覚悟しておくべきです。
登記・測量などの追加費用
隣地を購入する場合やセットバックを行う場合には、登記や測量の追加費用が発生します。
土地の境界確定や法務手続きも必要となるため、思った以上にコストが膨らむことがあります。
「建て替えは可能」と言われても、実際の費用負担を試算してから判断することが重要です。
\ 建て替えの可否を今すぐ確認! /
>>> 再建築不可物件の無料査定はこちら![]()
/ 条件次第で「再建築可能」に変わる安心感 /
再建築不可物件と住宅ローン

「再建築不可物件でも住宅ローンは使えるの?」と疑問に思う方は多いでしょう。
結論から言うと、ほとんどのケースで住宅ローンは利用できません。
ここではその理由と、代わりに利用できる可能性のあるローン、そして現金購入が多い背景について解説します。
なぜ住宅ローンが使えないのか
住宅ローンは、金融機関が「返済が滞ったときに物件を売却して回収できるか」を基準に審査しています。
つまり担保価値が低い物件には融資を行わないのです。
再建築不可物件がローンに不向きな理由を整理しましょう。
金融機関の担保評価の仕組み
銀行は融資を行う際、物件の担保価値を評価します。
再建築可能な土地なら「建て替えられる」ため価値がありますが、再建築不可物件は資産価値が大幅に低いと判断されます。
担保としての価値が低いため、金融機関は住宅ローンを認めにくいのです。
再建築不可がリスクと判断される理由
建て替えができないため、長期的に資産価値を維持できないと考えられます。
さらに、買い手が限定されるため流動性も低く、金融機関にとってはリスクの高い物件なのです。
その結果、住宅ローンの審査でほとんど通らないという状況になります。
利用できる可能性のあるローン
住宅ローンが難しいからといって、すべての融資が不可能というわけではありません。
条件次第で利用できるローンも存在します。
ここでは代表的な2つを紹介します。
リフォームローンの活用
建て替えはできなくても、リフォームで建物を活かすことは可能です。
その際に利用できるのがリフォームローンです。
金利はやや高めですが、再建築不可物件を活用する選択肢として検討する価値があります。
セカンドローンやフリーローン
金融機関によっては、担保を不要とするフリーローンやセカンドローンを提供しています。
借入額は少額に限られることが多いですが、修繕費や小規模リフォームには活用できます。
ただし返済負担が重くなる可能性があるため、無理のない利用が前提です。
現金購入が中心になる背景
住宅ローンが使えない以上、再建築不可物件は現金購入が中心となります。
現金で購入する人には、独自の目的やメリットがあります。
ここでは代表的な2つの背景を見てみましょう。
投資家需要が強い理由
投資家は再建築不可物件を低価格で仕入れられる点に注目しています。
リフォームして賃貸に出すなど、収益物件として利用できるからです。
ローンが使えない分、競合が少なく投資家にとっては狙い目の物件なのです。
相続物件の処分としての現金購入
相続した人が「現金で処分してしまいたい」と考えるケースも多いです。
再建築不可物件は放置すると固定資産税や修繕費がかかるため、早めに現金化したいニーズがあります。
現金購入者はこの需要を満たす形で取引を成立させるのです。
\ 本当に良かったという声が続出 /
>>> 再建築不可不動産の売却相談![]()
/ 相続・資産処分も現金化で安心 \
再建築不可物件の売却方法

「再建築不可だから売れないのでは?」と考える方は多いですが、実際には売却方法はいくつか存在します。
ただし通常の物件とは違い、売却の工夫や相手の選び方が重要です。
ここでは、仲介・隣地売却・自治体制度を活用する方法について解説します。
仲介で売却する場合
最も一般的な売却方法は、不動産会社を通じて仲介で売却する方法です。
時間はかかるものの、条件が合えば高値での売却も期待できます。
メリットとデメリットを整理してみましょう。
メリット(高値がつく可能性)
仲介を利用すれば、複数の買主候補にアプローチできます。
そのため、タイミング次第では市場価格に近い価格で売却できる可能性があります。
「少しでも高く売りたい」という人には向いている方法です。
デメリット(売れるまで時間がかかる)
一方で、再建築不可物件は需要が限られるため、売れるまでに数ヶ月〜1年以上かかることがあります。
さらに住宅ローンが使えないため、現金購入者に絞られてしまいます。
「早く現金化したい」という方には不向きです。
隣地所有者へ売却する方法
隣地を持つ人にとっては、再建築不可物件が大きな価値を持つ場合があります。
なぜなら、隣地と一体化することで再建築可能になるケースがあるからです。
この方法は、一般市場よりも有利な条件で売れる可能性があります。
価格が上がりやすい理由
隣地所有者が購入すると接道義務を満たせるため、土地全体の価値が上がります。
そのため、通常より高い価格での売却が成立するケースがあります。
これは再建築不可物件ならではの売却戦略です。
交渉の進め方
隣地所有者に直接話を持ちかけるか、不動産会社を通じて交渉を依頼するのが一般的です。
ポイントは、隣地のメリットを具体的に示すことです。
「再建築可能になる」という利点を伝えることで、スムーズな交渉につながります。
空き家バンクや自治体制度の活用
再建築不可物件の活用を支援する自治体も増えてきました。
特に地方では、空き家問題の対策として空き家バンク制度が整備されています。
補助金や支援制度を利用できることもあるので、調べてみる価値があります。
地方での需要を探す
地方では移住希望者や古民家再生を目的とする人からの需要があります。
「都会では売れにくい物件」でも、地方では新しい価値を見出されることがあるのです。
エリアによっては意外なニーズが眠っている可能性があります。
補助金制度の利用
自治体によっては、リフォーム費用や購入費用の一部を補助する制度があります。
これにより、買主にとって購入のハードルが下がり、売却がスムーズに進むケースがあります。
「自治体の補助金対象物件」としてPRできれば、売却チャンスを広げられます。
「空き家バンク・補助金活用」は、東京都の空き家支援ページと国交省“全国版空き家・空き地バンク参照:東京都の場合 住宅政策サイト
\ 売れないと思っていませんか? /
>>> 再建築不可物件の無料売却相談はこちら![]()
/ 専門業者なら売却ルートが見つかります \
再建築不可物件の買取方法

「売りたいけど、なかなか買い手が見つからない…」
そんなときに有効なのが 権利関係に強い不動産買取業者への売却 です。
これまでの内容でお分かりのように、「再建築不可」には第三者の権利が絡みます。
これを解決するには、専門知識はもちろんですが実績が大きな武器になります。
実績の多い買取業者に関しては こちら をご確認ください。
また、仲介よりもスピーディーに現金化できるため、多くの方が選んでいる方法です。
ここでは、買取の流れ・価格の特徴・向いている人の条件について解説します。
\ 共有名義・相続トラブルも対応! /
>>> 権利関係に強い買取業者へ相談![]()
/ 実績豊富な専門業者が複雑案件でも解決 \
不動産買取業者に依頼する流れ
買取業者に依頼する際の流れはシンプルで、仲介売却に比べると短期間で完了します。
「とにかく早く手放したい」という方にとって最適な方法です。
実際のステップを見ていきましょう。
査定から契約までのステップ
まずは業者に査定を依頼し、価格提示を受けます。
その後、条件に納得できれば契約へと進みます。
仲介と違って買主探しが不要なので、手続きがスムーズです。
現金化までの期間
買取の場合、最短で1週間〜1ヶ月で現金化できることがあります。
急ぎで資金が必要な場合や、相続税の納付期限が迫っている場合などにも有効です。
スピードを重視するなら、仲介より買取が有利です。
買取価格の特徴
スピーディーに現金化できる一方で、仲介売却と比べると価格は低くなりがちです。
その理由とメリットを理解しておきましょう。
仲介より低い理由
買取業者は買い取った物件を再販売するため、リスクを負う必要があります。
そのため、価格は市場価格の6〜8割程度に抑えられることが多いです。
物件によってはさらに安くなる場合もあります。
しかし、権利関係を自分で動いたり、専門家に依頼する負担は想像以上に大きいものです。
「高値売却」より「確実な売却」を重視する取引形態といえます。
スピード重視の取引メリット
価格は下がりますが、確実に早く現金化できるのが大きなメリットです。
特に「時間をかけても売れないリスク」を避けたい方に適しています。
精神的な負担を減らせるのも、買取を選ぶ大きな理由のひとつです。
どんな人が買取を選ぶべきか
すべての人にとって最適とは限りませんが、条件によっては仲介よりも適しているケースがあります。
特に「スピード」と「確実性」を重視する人におすすめです。
代表的なケースを紹介します。
早く現金化したいケース
相続税の支払いや急な資金需要がある場合は、買取が最も適しています。
仲介売却では時間がかかりすぎて間に合わないこともあるからです。
「少し安くても早く売りたい」という方には買取がベストな選択肢です。
相続や共有名義で困っているケース
共有名義の物件や相続で揉めている物件は、市場での売却が難しいケースが多いです。
そのような場合でも、買取業者なら柔軟に対応してくれることがあります。
「複雑な事情を抱えた物件」ほど、買取という出口が役立ちます。
\ 複雑な物件でも大丈夫! /
>>> 再建築不可不動産の買取相談![]()
/ 共有名義・相続トラブルもプロが解決 \
まとめ|再建築不可物件の出口戦略を早めに決める
ここまで再建築不可物件の特徴やリフォーム・売却・買取の方法について解説してきました。
重要なのは「放置しないこと」です。何もせずに持ち続ければ、税金や修繕費がかかり続け、資産価値も下がっていきます。
出口戦略を早めに決めることで、損失を減らし、むしろ資産として活用することも可能になります。
選択肢の比較
再建築不可物件には複数の対応方法があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の状況に合わせて選択することが大切です。
代表的な選択肢を整理してみましょう。
リフォーム vs 売却 vs 買取
リフォームすれば賃貸物件として活用でき、継続的な収入を得られる可能性があります。
売却は時間はかかりますが、条件が合えば高値での取引ができるチャンスがあります。
一方で買取は価格は低くなりがちですが、短期間で現金化できるという大きなメリットがあります。
隣地交渉という選択肢
再建築不可物件ならではの方法として隣地所有者との交渉があります。
隣地と一体化させることで再建築可能となり、通常より高い価格で売却できる可能性があるのです。
「隣地が欲しがる土地」なら、思わぬ好条件での売却が実現することもあります。
専門家に相談する重要性
出口戦略を決める上で、専門家のアドバイスを受けることは非常に有効です。
法律や不動産の知識が必要となるため、自己判断だけではリスクが高いからです。
ここでは相談すべき専門家と、そのメリットについて解説します。
不動産会社・弁護士・司法書士の役割
不動産会社は査定や売却戦略を提案してくれます。
弁護士は相続や権利関係のトラブル解決をサポートします。
司法書士は登記や名義変更などの法務手続きを代行してくれるため、スムーズに進められます。
無料相談を活用するメリット
多くの専門家や買取業者では、無料相談を受け付けています。
気軽に相談できるため、現状を整理したり複数の意見を比較するのに最適です。
「もっと早く相談していれば良かった」と後悔する前に、まずは一度問い合わせてみましょう。
\ もう悩まないで大丈夫!ワンストップで解決に /
>>> 再建築不可物件の売却・買取ルートを確認![]()
/ 複雑な事情も専門業者が安心サポート \



コメント