ここでは、火災保険は空き家に適用できるのか、全労済を中心に加入条件と注意点がわかります。
「空き家でも火災保険に入れるはず」と思っていたのに、いざ調べると断られた――
そんな声は少なくありません。
特に全労済は、原則として居住住宅が対象となるため、空き家では注意が必要です。
全労済や県民共済などとの違い、加入可否の分かれ目、確認すべきポイントをわかりやすく整理しました。
後悔しない判断のために、ぜひ最後までご覧ください。
\ 今の空き家に最適な解決策が分かる /
>>> その場でわかる査定金額!空き家・中古戸建ての買取専門店に相談
![]() /手数料0円/キャンセル自由/現況そのままOKです\
/手数料0円/キャンセル自由/現況そのままOKです\
「ほかのサービスとも比べてから決めたい」方は
>>> 訳あり物件の買取サービス比較ページはこちら
なお、全労済だけでなく空き家向け火災保険全体を俯瞰できる親記事も用意しています。
全労済の火災保険は空き家でも加入できる?

「全労済の火災保険は、空き家でも入れるの?」──この疑問を持つ方はとても多いです。
家を相続したけれど誰も住んでいない、転勤でしばらく不在になる…
そんな状況で、火災保険の補償がどうなるのか不安になりますよね。
結論から言うと、全労済の火災保険(住まいる共済)は「実際に人が住んでいる家」が対象であり、空き家は原則として加入できません。
ただし、例外的に補償が継続できるケースもあります。
全労済(住まいる共済)の基本仕組み
まずは、全労済(正式名称:全国労働者共済生活協同組合連合会)が提供する「住まいる共済」の基本を見ていきましょう。
住まいる共済は、火災・落雷・風災・盗難など、生活の中で起こり得るさまざまなリスクをカバーする共済制度です。
ただし、加入対象はあくまで「人が実際に居住している住宅」。
つまり、人が住んでいない空き家は“住宅”とみなされないため、契約できないケースがほとんどです。
- 全労済は全国規模で運営されており、手頃な掛け金で補償が受けられる。
- 正式名称は「住まいる共済」。火災・落雷・風災・水害・盗難などを幅広く補償。
- 対象は「居住実態がある住宅」に限定され、空き家は契約の対象外となる。
共済という仕組みは、加入者同士が助け合う“相互扶助”を前提としており、リスクの高い物件(無人の空き家など)は引き受けが難しいのが実情です。
そのため、全労済では空き家専用の火災保険商品は存在しません。
空き家では加入できない理由
では、なぜ空き家は補償の対象外になるのでしょうか?理由を知っておくことで、リスクへの備え方も変わってきます。
全労済の共済規約には、「住宅物件であること」という明確な条件があります。
つまり、そこに人が生活していなければ住宅とはみなされません。
また、無人状態では火災・放火・漏電などの事故リスクが高くなるため、共済の運営上、引き受けが制限されるのです。
- 空き家は管理が行き届かず、火災発生率が居住中の家の約3倍に上るといわれています。
- 放火や漏電による出火のリスクが高く、共済の補償対象外となりやすい。
- 2024年以降は新規契約で空き家を対象にできず、既契約者についても「空家届」を提出した場合、原則として補償対象外となります。
ただし、共済側が承諾した場合に限り、一定期間のみ補償が継続されるケースもあります。
つまり、たとえ保険料を払っていても、「居住実態がない」と判断されれば補償を受けられない可能性が高いのです。
この点を知らずに「入っているから大丈夫」と安心してしまうのは、非常に危険です。
こうした制度上の落とし穴は、保険だけを見ていても判断がつかないケースが少なくありません。
埼玉で不動産に33年以上携わってきた現場経験をもとに、売却ありきではなく、状況の整理から一緒に行っています。
例外的に継続可能なケース
ただし、すべての空き家が一律に契約できないわけではありません。
一時的に不在となるケースや、管理状態が良好であれば、一定条件のもとで補償を継続できる場合もあります。
以下のような状況では、共済組合の判断次第で「住宅」とみなされる可能性があります。
- 転勤や入院など短期間の不在であり、家財や電気・水道契約を継続している。
- 家族や業者による定期的な管理・巡回が行われており、完全放置でない。
- ただし、補償範囲が制限されることがあり、共済担当窓口への事前相談が必須です。
このように、空き家でも条件次第で継続できることはありますが、「無申告で放置している状態」では補償対象外になるため注意が必要です。
判断が難しい場合は、必ず全労済の窓口で現況を説明し、対応を確認しましょう。
空き家扱いになる条件とは?(住んでいない期間の基準)
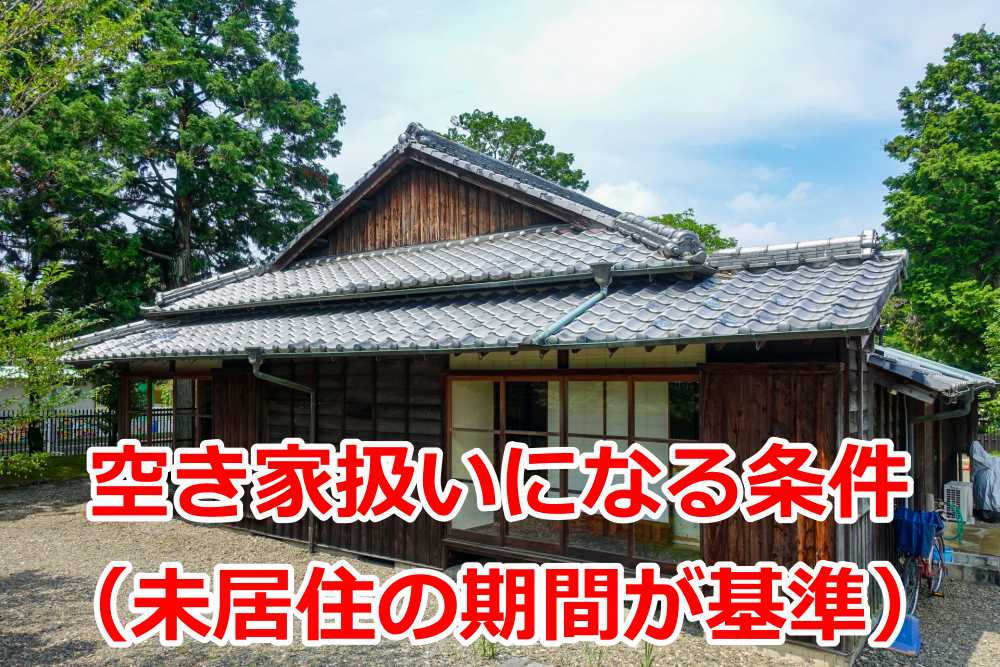
「うちはたまに帰っているから、空き家ではないはず…」と思っていませんか?
実は、保険や共済の世界では、生活実態の有無で「空き家」かどうかが明確に判断されます。
ここでは、空き家と見なされる基準や期間の目安、そして空き家と判断された場合のリスクについて詳しく解説していきます。
「空き家」と判断される一般的な基準
まずは、どのような状態が「空き家」と見なされるのかを知っておきましょう。
この基準は、自治体や保険会社によって多少の差がありますが、共通しているのは“人が実際に生活しているかどうか”という点です。
次のような状態が続くと、全労済をはじめ多くの保険・共済では「空き家」扱いとされる可能性があります。
- 3か月以上居住実態がない。
- 電気・ガス・水道などのライフライン契約が停止されている。
- 郵便物・新聞の受け取りがなく、生活の痕跡が見られない。
このような状態が続くと、保険契約上「住宅ではなく物件」と判断され、火災保険の補償対象外になる場合があります。
特に、長期間帰省や相続放置によって空き家化しているケースは、早めの確認が大切です。
「一時不在」と「空き家」の違い
「一時的に家を空けているだけなのに、空き家扱いされたら困る…」という声も多く聞かれます。
そこで重要なのが、“一時不在”と“空き家”の明確な違いを理解することです。
この違いを正しく認識しておけば、契約上のトラブルを防ぐことができます。
- 一時不在: 出張や療養、転勤などで一時的に家を離れている状態。家具や家財、電気・水道などの契約が続いており、管理もされている。
- 空き家: 長期間にわたって無人で、管理や生活の痕跡がほとんどない状態。ライフラインも停止しており、住宅としての実態が失われている。
ポイントは、「生活の痕跡」があるかどうかです。
電気が通っていない、ポストに郵便物が溜まっている、草木が伸び放題…これらは明確に「空き家」と判断される要素です。
逆に、定期的な換気や清掃、ライフラインの維持があれば、「一時不在」として扱われる可能性が高くなります。
空き家と判断された場合のリスク
もしも全労済などで「空き家」と判断されてしまった場合、いくつかのリスクが生じます。
知らないうちに契約条件が変わっていた、補償が打ち切られていた、というケースも少なくありません。
代表的なリスクは以下の通りです。
- 共済契約の更新が拒否される、または補償が途中で打ち切られる。
- 火災・漏電などの事故が発生しても、「住宅扱いでない」とされ保険金が支払われない。
- 再度加入する際の審査が厳しくなり、保険料が高額になるケースも。
こうしたリスクを避けるためには、現状を正直に申告し、共済組合または保険会社へ早めに相談することが大切です。
また、空き家のままにしておくのではなく、定期管理や巡回サービスを利用して「一時不在」扱いを維持する工夫も有効です。
万が一、空き家と判断された場合でも、損保系の火災保険や専門買取サービスを活用することで、リスクを最小限に抑えることができます。
「結局どの保険が空き家に向いているの?」と悩んでいる方は、こちらで全体像をまとめています。
全労済が補償対象外になるケース

「保険に入っているから大丈夫」と思っていても、いざ火災が起きたときに保険金が支払われないケースが存在します。
特に全労済(住まいる共済)は、“居住している住宅”が前提のため、空き家状態では補償の対象外になる可能性が高いのです。
ここでは、具体的にどんなケースで「おりない」「補償されない」と判断されるのかをわかりやすく解説します。
火災保険金が「おりない」主な理由
火災が発生しても、すべてのケースで保険金が下りるわけではありません。
特に、空き家や長期不在の住宅では「契約条件に違反している」とみなされることが多く、支払い対象外になることがあります。
全労済の火災保険(住まいる共済)で「おりない」典型的な理由は以下の通りです。
- 居住実態がない(完全無人の空き家)。
- 建物の管理不備による火災(放火・老朽化・漏電など)。
- 契約時に空き家化を報告していない(申告義務違反)。
このような場合、事故後の調査で「契約条件に適合していない」と判断され、保険金が支払われないことがあります。
特に、“居住実態なし”と判断された場合は原則不払いになるため注意が必要です。
保険加入時の申告内容(誰が住んでいるか・どんな利用目的か)と、実際の状況が一致しているかを常に確認しておきましょう。
契約違反と判断されるリスク
全労済の共済契約では、“契約内容と実態が異なる場合”、契約そのものが無効になるリスクがあります。
空き家化したのに連絡をしないまま契約を続けていると、事故時に「契約違反」と判断され、補償を受けられなくなることもあります。
次のような状況は特に注意が必要です。
- 「住宅共済」で契約していながら空き家化しており、事故後の現地調査で不払いになるケース。
- 空き家転用を申告せず契約を継続していたため、契約そのものが無効とされるケース。
全労済を含む共済制度は、営利目的の保険とは異なり「加入者間の公平性」を重視しています。
そのため、意図的な申告漏れや、実態との乖離があると“共済全体の信頼性を損なう行為”として扱われ、厳格な対応を取られる場合があります。
「誰も住んでいないけど、とりあえず契約を続けておこう」と放置するのは非常に危険です。
具体的な不払い事例(想定)
ここでは、実際に起こり得る「不払い」のケースを具体例で紹介します。
これらはあくまで想定ですが、全労済の規約や過去の事例に照らすと十分あり得る内容です。
似たような状況に心当たりがある場合は、早めに見直しを検討してください。
- 家財撤去後の火災 → 家具や家電がない状態では「住宅共済」条件に不適合とされ、補償対象外に。
- 漏電出火 → 老朽化や電気設備の劣化による出火は“管理不備による事故”と判断され、自己責任扱いになる。
- 放火被害 → 管理不十分で放火されやすい状態だった場合、「予防措置を怠った」として補償対象外にされる可能性がある。
特に、「事故後の調査」で実態が空き家だと判明した場合、過去の支払いも遡って取り消されることがあります。
これを避けるためには、空き家化した時点で速やかに共済へ報告し、適切な補償内容に切り替えることが大切です。
また、空き家でも加入できる火災保険や管理サービスを併用することで、リスクを最小限に抑えられます。
他の共済・保険との違い(県民共済・JA共済比較)

「全労済だけが空き家に入れないの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
実は、県民共済やJA共済などの他の共済も、空き家への補償には制限があります。
ここでは、主要な共済制度の特徴を比較しながら、どのような違いがあるのかをわかりやすく整理していきます。
県民共済・全労済・JA共済の比較表
空き家でも火災保険に加入すべきか悩む方は多いですが、共済系の保険が対応しているかどうかは意外と知られていません。
特に人気のある「県民共済」「全労済」「JA共済」は、それぞれに特徴や制限があり、空き家の補償対象かどうかは契約前にしっかり確認する必要があります。
共済とは、同じ地域や職域の人たちが掛け金を出し合い、万が一のときに助け合う仕組みです。
そのため、どの共済も「生活の場=居住用住宅」を前提としており、空き家は原則として対象外になります。
ここでは、これら3つの共済について、空き家に関する対応状況や補償内容、加入条件などを比較してご紹介します。
選択の参考にしてください。
| 比較項目 | 県民共済 | 全労済 (全国労働者共済) |
JA共済
(農協共済) |
| 空き家への加入可否 | ❌ 原則不可(居住用に限る) | ❌ 原則不可(空き家は対象外) |
⭕ 条件付きで可能(要審査)
|
| 主な補償内容 | 火災、落雷、風災など | 火災、落雷、風災、水ぬれなど |
火災、落雷、風災、水ぬれ、盗難など
|
| 掛金(例) | 月1,000円〜(住居の広さで変動) | 月1,000円〜(地域や建物条件で変動) |
年間1万〜3万円台(建物評価による)
|
| 空き家補償の有無 | ❌ なし | ❌ なし |
⭕ 別途契約で対応可(商品による)
|
| 特徴・備考 | 共済金の支払いがスムーズ | 対象が限定的(契約対象は基本居住中) |
地方によって取り扱い・条件が異なる
|
| 加入のしやすさ | ◎ 簡単(地域住民ならOK) | ○ 組合員または勤労者向け |
△ 組合員登録が必要(農協との関係)
|
加入条件を比較しても不安が残るなら、根本的な解決を考えてみませんか?
ご覧の通り、どの共済も掛け金が安く、火災を中心とした補償が特徴です。
しかし、空き家の場合は原則として契約・継続ともに不可であり、例外的にJA共済が地域判断で対応することがある程度です。
また、JA共済は農村部などで自然災害を想定した補償が手厚い点が特徴的です。
共済の共通デメリット
どの共済も安心感や低コストが魅力ですが、いくつかの共通した弱点もあります。
空き家所有者にとっては、これらの点が「加入できない」「補償されない」原因になるため、しっかり理解しておくことが大切です。
主なデメリットは次の3つです。
- 補償範囲が限定的で、風水害や地震には特約が必要になる。
- 空き家では契約・更新ともに不可で、補償が適用されない。
- 住宅実態確認の手続きが複雑で、居住証明や現地確認を求められるケースもある。
つまり、共済は「今まさに生活している家」を守る制度であり、長期間無人の住宅や相続したまま放置している家には不向きなのです。
万が一の火災リスクが高まる空き家の場合、共済ではなく損害保険型(損保)の火災保険を検討するのが現実的です。
損保型火災保険との違い
共済と損害保険(損保)は、そもそも仕組みが異なります。
共済が「相互扶助型(助け合い)」なのに対し、損保は契約に基づくリスク補償型であり、個別の条件に応じて柔軟に対応できる点が強みです。
そのため、空き家や老朽化住宅など、通常の共済でカバーできないケースでも、損保型なら加入できる可能性があります。
- 損保型は「一般物件」として空き家でも加入可能。
- 保険料は共済より高いものの、補償範囲が広く賠償・盗難・管理不備も対象にできる。
たとえば、ソニー損保・東京海上日動・損保ジャパンなどでは、定期巡回や電気契約の維持など一定の条件を満たすことで、空き家でも契約が可能です。
掛け金は高くなるものの、補償の確実性や事故時の対応スピードを考えると、安心感は大きいといえます。
つまり、「今の家をしばらく空ける」「誰も住まなくなった」という場合は、共済から損保型への切り替えが最もリスクを減らす選択肢になります。
空き家の火災保険を広く比較したい方は、こちらをご覧ください。
補償が難しい空き家をどう守る?(3つの対策)
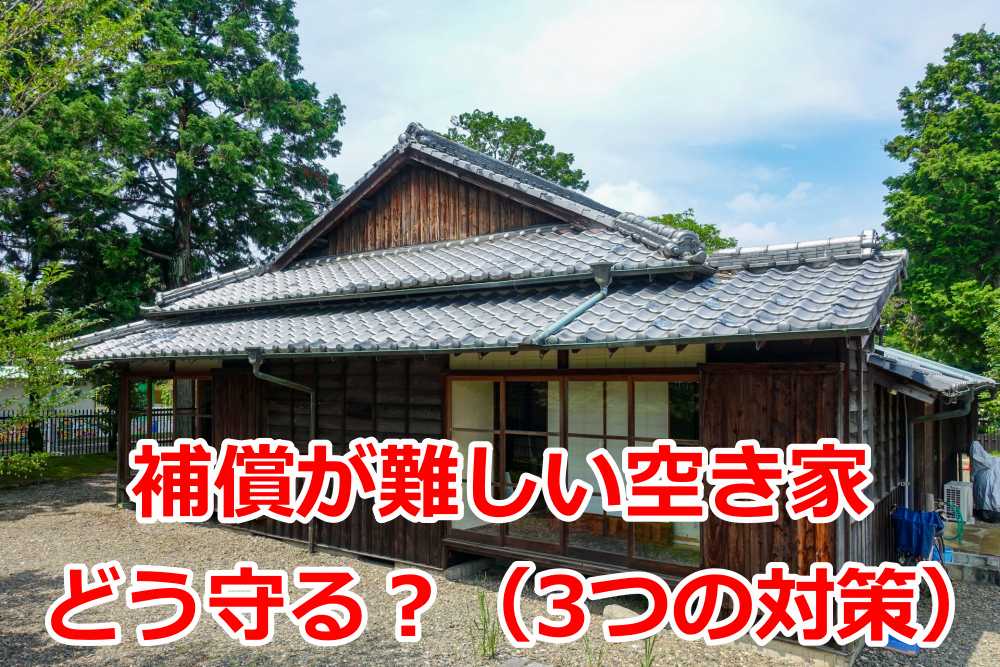
「空き家だと火災保険に入れない…」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。
ですが、諦める必要はありません。管理方法や保険の選び方を工夫することで、空き家でもリスクを軽減することは可能です。
ここでは、補償が難しい空き家を守るための3つの実践的な対策を紹介します。
対策①:空き家でも加入できる火災保険を選ぶ
まず最初に考えたいのは、「空き家でも加入できる火災保険」を選ぶことです。
全労済や県民共済などの共済型では加入が難しい場合でも、損害保険会社の「一般物件」プランなら契約できるケースがあります。
代表的な保険会社として、ソニー損保・東京海上日動・損保ジャパンなどが挙げられます。
- ソニー損保・東京海上・損保ジャパンなどが「一般物件」として引き受け可。
- 契約条件:定期的な管理・電気契約の維持・建物の健全な状態が求められる。
空き家向けの火災保険では、通常より保険料がやや高くなる傾向があります。
しかし、火災や放火などのリスクを考えれば、「補償を受けられる安心」のほうが大きなメリットです。
また、契約前には必ず「空き家であること」を申告するようにしましょう。隠して契約すると、事故時に補償対象外となるおそれがあります。
対策②:管理委託・見回りサービスを利用
2つ目の対策は、空き家の定期管理をプロに任せることです。
月5,000円前後で、見回り・写真報告・通風・除草などを行う管理サービスが増えています。
管理を行うことで建物の劣化を防げるだけでなく、火災保険や共済の審査時に「管理実績」として有利に働くケースもあります。
- 月5,000円前後で定期巡回・報告書付きのサービスを利用できる。
- 定期管理を行うことで、火災保険の加入・継続審査が通りやすくなる。
最近では自治体や不動産会社が提携している「空き家管理サポート」も増えており、放置リスクの軽減に役立ちます。
たとえば、定期的に人が出入りしていると放火リスクが下がり、保険会社の評価も改善されるのです。
つまり、管理を「しているか・していないか」が、補償の可否を分ける重要なポイントになるということです。
対策③:売却・利活用によるリスク回避
最後の選択肢として、「空き家を所有し続けない」という決断も視野に入れておきましょう。
管理や保険を維持することが負担に感じる場合は、売却や利活用によってリスクをゼロにするのが最も現実的です。
特に近年は、空き家や訳あり物件を専門に買い取る業者が増えており、現状のままでも売却できるケースがあります。
- 保険料・固定資産税・管理コストをまとめて削減できる。
- 「訳あり物件」でも、ワケガイやラクウルなどの専門買取業者ならスピード売却が可能。
放置するほど老朽化が進み、火災や倒壊などのリスクも高まります。
もし将来的に使う予定がないなら、早期の売却・現金化が結果的に家計の負担を減らす最善策になります。
空き家を守る方法は「保険」「管理」「売却」の3つしかありません。
どの方法を選ぶかは、あなたの生活スタイルと費用負担のバランスで決めるのが賢明です。
\ 放置した実家も“現況のまま”でOK /
>>> その場でわかる査定金額!空き家・中古戸建ての買取専門店に相談
![]() /今の状況に合う解決策がすぐ分かります\
/今の状況に合う解決策がすぐ分かります\
「ほかのサービスとも比べてから決めたい」方は
>>> 訳あり物件の買取サービス比較ページはこちら
火災保険 空き家 全労済でよくある質問(FAQ)

ここでは、「全労済の火災保険」と「空き家」に関してよく寄せられる質問をまとめました。
空き家の補償範囲や乗り換え時期など、実際に悩みやすいポイントを中心に解説します。
Q1. 全労済の火災保険は空き家でも継続できますか?
A. 原則として継続はできません。空家届を提出すると、住宅としての補償は原則終了となります。ただし、一時的な不在などと認められ、共済側の承諾がある場合に限り、一定期間のみ補償が継続されることがあります。
Q2. 空き家期間が短い場合(数か月)でも補償対象外になりますか?
A. 出張や入院などの一時不在であれば補償継続は可能です。ただし、3か月以上の無人期間が続くと、空き家扱いとして除外される場合があります。
Q3. 共済より損保のほうが空き家には向いていますか?
A. はい。損保(損害保険)なら「一般物件」扱いで加入できる商品があります。共済は生活の場を前提としているため、空き家では補償対象外になりやすいです。
Q4. 火災保険料の目安はいくら?
A. 空き家向け火災保険の保険料は、年間1〜6万円程度が相場です。建物の構造(木造・鉄骨など)や築年数、管理状況によって変動します。
Q5. 補償されない火災にはどんな例がありますか?
A. 放火・漏電・老朽化など、管理不備が原因の火災は補償対象外となります。特に無人状態が長いと「自己責任」と判断されやすいです。
Q6. 全労済や国民共済を解約して損保に乗り換えるタイミングは?
A. 空き家化が明確になった段階で早めに乗り換えるのがおすすめです。事故が発生してからでは補償を受けられないケースがあります。
Q7. 空き家を手放す方法はありますか?
A. はい。専門買取業者(ワケガイ・ラクウルなど)なら、現状のままでもスピード売却が可能です。査定から現金化まで最短3日で完了する場合もあります。
※ 空き家の扱いは建物の使用状況や管理状態によって判断されるため、必ず事前に全労済の窓口で確認してください。
空き家の火災保険を広く比較したい方は、こちらをご覧ください。
まとめ:全労済は空き家に非対応。早めの代替策を
ここまで解説してきたように、全労済や国民共済の火災保険は「居住実態のある住宅」を前提としており、空き家は補償対象外です。
もし今の家が空き家化している、または将来的に誰も住まなくなる見込みがあるなら、早めに代替策を講じることが重要です。
- 全労済・国民共済ともに「居住実態」が必須条件。
- 空き家では補償されず、損保系火災保険の検討が現実的。
- 保険+管理の両輪で、火災・倒壊・放火リスクに備える。
空き家を守るための選択肢は大きく3つあります。
- 空き家対応の火災保険に切り替える
- 管理サービスを利用して維持管理を強化
- 現状のまま専門業者に売却する
とくに「誰も住まない」「維持が難しい」と感じている場合は、保険や管理を検討するよりも、専門買取業者に相談するほうがリスクを最小化できます。
ワケガイやラクウルのような専門業者であれば、解体不要・現状のまま・最短3日で現金化が可能です。
埼玉で不動産に33年以上携わってきた現場経験をもとに、売却ありきではなく、状況の整理から一緒に行っています。

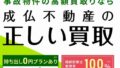

コメント