「共有者の同意が得られない」「連絡がつかない人がいる」「相続で名義人が増えてしまった」
──そんな状況に不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
共有名義の不動産が「売却できない」と言われます、なぜ?
ここではその理由や、実際に起こりやすいトラブル、そして解決策までをわかりやすく解説します。
これを読み終わるころには、売却への道筋が見えるはずです。
まずは気軽に読み進めてみてください。
共有名義の不動産はなぜ「売却できない」と言われるのか?
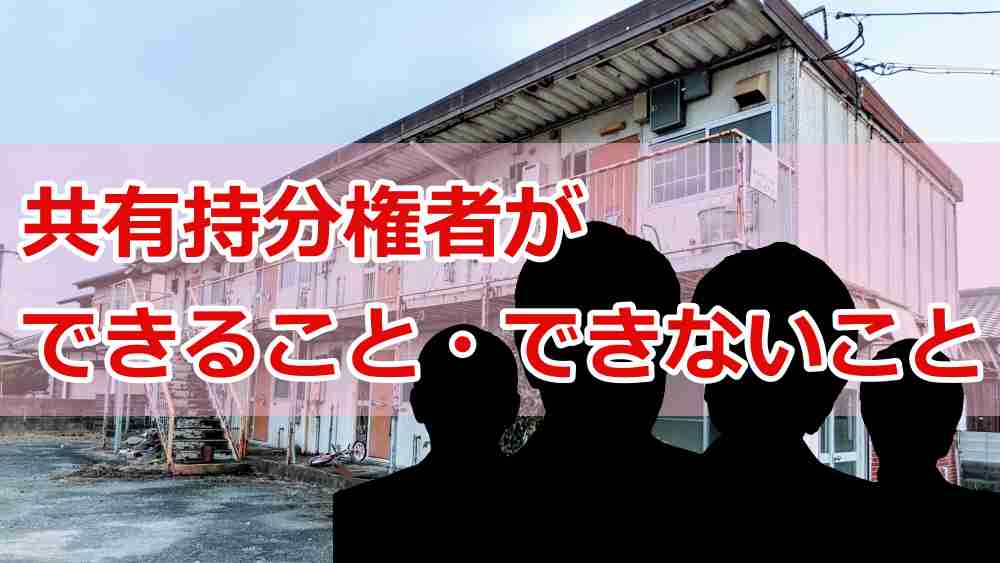
「共有名義 売却 できない」といわれる背景には、売却が共有者全員の同意を要するというルールがあります。
この同意要件は法律上「処分行為」に当たるため、だれか一人の判断だけでは前に進めません。
同意の取り付け、書類準備、日程調整に時間がかかり、結果として売却できない理由の核心になりがちです。
共有名義と単独名義の違い
単独名義は、所有者本人の判断で売却方針や価格を決めやすい形です。
一方の共有名義は、持分の大小に関わらず、重要な決定には全員の合意形成が必要です。
意思決定の起点が「一人」か「複数」かで、スピードと難易度が大きく変わります。
単独名義:1人の意思で売却可能
単独名義なら、売出価格の見直しや買主の条件調整も、所有者の裁量で迅速に進められます。
手続きや交渉がシンプルで、結果として成約までの期間が短くなりやすいのが特長です。
「値下げのタイミング」や「契約条件の最終決裁」も一任できるため、機動的な意思決定が可能です。
共有名義:全員の同意が必要
共有名義では、売却は共有者全員の同意が必須です。
価格・引渡し時期・残置物・修繕範囲など、細部まで認識合わせが必要になるため、決定が遅れがちです。
一人でも反対すれば契約は成立しませんので、事前の合意形成と情報共有がカギになります。
共有持分権者ができること・できないこと
共有不動産の行為は、大きく「単独でできる」「過半数で決める」「全員一致が必要」に分かれます。
どこまで単独で動けるのかを正しく理解しておくと、ムダな衝突や手戻りを防げます。
特に「売却」は最も重い決定に当たるため、ルールの把握は不可欠です。
単独でできる行為(保存・居住など)
雨漏り修繕やフェンス補修などの保存行為、自分や家族の居住などは、単独で実行できます。
現状維持や安全確保に関する行為は、全体の利益を守るために認められている範囲です。
ただし、用途や収益構造を変える行為には当たりませんので注意が必要です。
過半数で決められる行為(短期賃貸・リフォーム)
原状回復や軽微なリフォーム、短期賃貸などの管理行為は、過半数の同意で決められます。
「過半数」を誰がどう確保できるかは、持分割合の確認が前提になります。
合意プロセスや記録化を丁寧に行うと、のちのトラブル予防に効果的です。
全員一致が必要な行為(売却・抵当権設定など)
売却・長期賃貸・抵当権設定・分筆などの処分行為は、全員一致が必要です。
最も利害が動く意思決定なので、価格・条件・税務の見通しまで共有して合意を取り付けます。
専門家の同席や議事録化により、合意の質とスピードを両立させましょう。
持分割合が売却に与える影響
「誰がどれだけ決められるか」は、実は人数ではなく持分割合で決まります。
過半数の管理行為と、全員一致の処分行為で、必要となる同意のハードルが変わります。
まずは登記情報や相続協議書で、足元の権利関係を正確に把握しましょう。
過半数を確保できるかが分かれ目
管理行為は「過半数の持分」で決まります。
誰が過半を握るかで、賃貸方針や改修の意思決定がスムーズにも停滞にもなります。
売却戦略の前段として、持分マップを作って見える化しておくと有効です。
登記簿・相続協議書で確認する方法
最新の登記簿で持分と共有者を確認し、相続協議書で配分や合意事項をチェックします。
代表者のみ手元にあることが多い固定資産税通知は、内訳が載らないケースが一般的です。
正確さを期すなら、登記情報の取得と全員への情報共有が近道です。
共有名義の不動産が売却できない典型的な理由
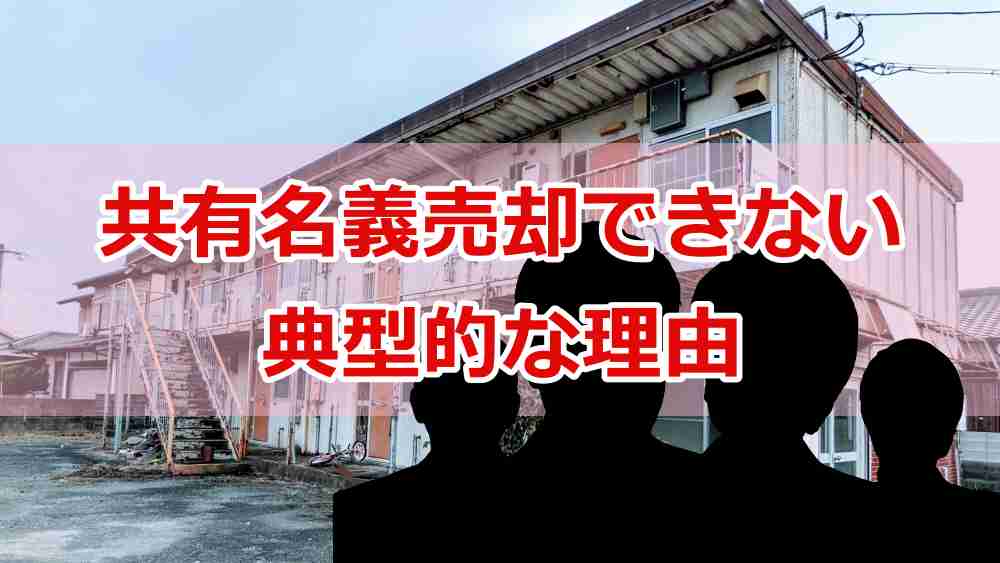
「共有名義 不動産 売却 トラブル」で検索する方の多くは、売却が思うように進まない現実に直面しています。
その背景には全員の同意が必要というルールと、それに伴う現実的な障害があるのです。
ここでは、売却を阻む典型的な理由を整理し、なぜ「売却できない」と言われるのかを解説します。
全員の同意が得られないケース
共有名義の最大の壁は共有者全員の同意です。
だれか一人でも反対すれば契約は成立しません。
このため、合意形成が難航しやすいのです。
1人でも反対すれば契約は不成立
売却は処分行為にあたるため、全員一致が必須です。
少数派でも反対すれば契約が止まってしまい、時間や費用だけが消耗することになります。
「同意が揃わない=売れない」という厳しい現実を避けるには、事前調整が不可欠です。
売却価格や時期を巡る意見対立
「早く安くても売りたい人」と「相場以上で売りたい人」の意見がぶつかることはごく普通です。
売却価格や時期の判断基準が揃わないと、交渉が前に進みません。
このようなときは、不動産鑑定士など第三者の客観的評価を利用するのも解決の一手です。
他の共有者と連絡が取れないケース
共有者の所在や連絡先が不明になると、売却の同意が得られず、取引は進みません。
特に相続が繰り返された物件では、権利関係が複雑化していることが多いです。
このような場合には法的な制度を活用する必要があります。
相続登記未了で権利者不明になる場合
相続登記が放置されると、共有者が誰か分からない状態になります。
権利関係が曖昧なままでは、買主がついても契約できません。
まずは相続登記の完了が最優先です。
不在者財産管理人制度の活用
共有者が行方不明で連絡が取れないときは、家庭裁判所に申立てを行い「不在者財産管理人」を選任できます。
この管理人が不在者の代わりに意思表示できるため、売却が可能になります。
手続きには時間と費用がかかりますが、前に進める数少ない方法です。
夫婦共有名義と離婚時のトラブル
夫婦で購入した不動産は、離婚時の財産分与で大きな争点になります。
名義上の持分割合と実際の取り分が異なることがあり、トラブルを招きやすいのです。
特に離婚前の持分売却には注意が必要です。
財産分与でもめやすい理由
たとえば登記上「夫60%・妻40%」であっても、離婚時には原則50%ずつの分与が求められます。
この差が争いの火種となりやすいのです。
事前に弁護士や司法書士に相談しておくと安心です。
離婚前に持分売却すると発生する問題
一方の共有者が離婚前に持分を売却すると、配偶者の取り分が侵害される可能性があります。
その結果、追加で支払いを求められるなど予期せぬ問題につながります。
離婚前の独断での売却はリスク大と覚えておきましょう。
相続で共有者が増え続けるリスク
相続が繰り返されると、共有者がどんどん増えていきます。
人数が増えるほど意思統一は難しくなり、合意形成に時間がかかります。
さらに税金や管理費の分担も複雑化するため、トラブルの温床になりやすいのです。
代を重ねるほど意思統一が困難に
10人以上の共有者が関与するケースもあり、売却どころか管理の意思決定すら難しくなります。
この状況を避けるには、早めの名義整理が重要です。
換価分割や代償分割などで、単独所有にまとめる工夫が求められます。
管理・税金負担も複雑化
固定資産税や修繕費の請求が共有者全員に分散し、誰がどの割合で負担するのか混乱しやすくなります。
支払いが滞ると、延滞金や差押えといったリスクも生じます。
共有名義のまま放置せず、早めの対応が肝心です。
共有名義不動産で起こりやすいトラブルと実例
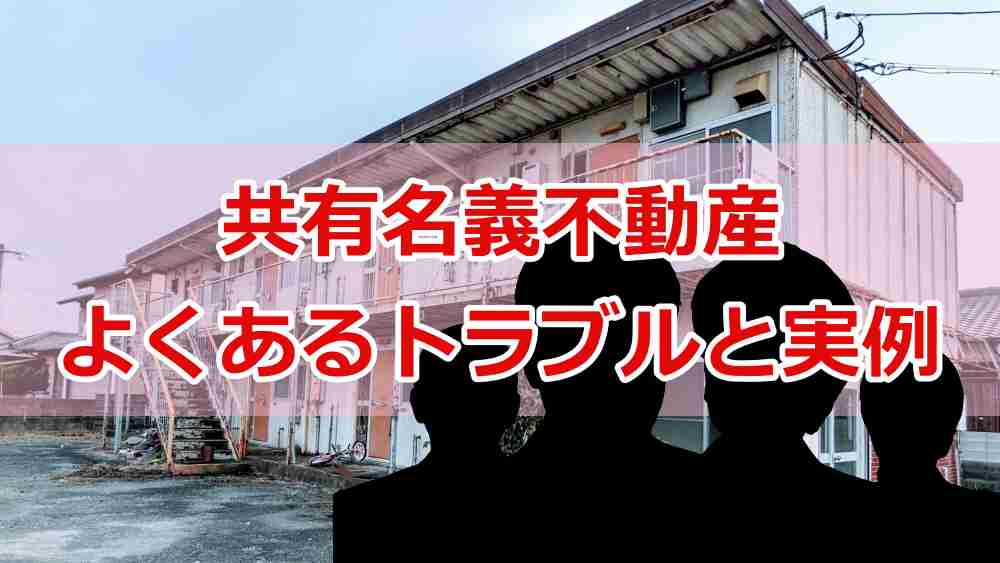
「共有名義 売却 できない」と悩む背景には、単に売却が進まないだけでなく、そこから派生するトラブルがあります。
合意が取れないまま放置すれば、関係性が悪化したり、法的な争いに発展することも少なくありません。
ここでは、実際によくあるトラブル事例を取り上げ、その原因と解決のヒントを紹介します。
共有者の一方が勝手に売却を進めてしまう
不動産の売却は共有者全員の同意が必要です。
それにもかかわらず、共有者の一人が独断で契約を進めてしまうと、重大なトラブルになります。
この場合、契約そのものが無効とされる可能性が高いのです。
全員同意なしの契約は無効
売却は処分行為に該当し、全員一致が絶対条件です。
無断で契約しても法的に効力を持たず、買主に対しても売却は成立しません。
結果として「時間もお金も無駄にした」というケースが多発しています。
損害賠償に発展するケース
無効契約により買主へ損害が発生した場合、売却を進めた共有者個人が損害賠償責任を問われる可能性があります。
また、他の共有者からも「勝手に進めた」として訴えられることもあります。
一度こじれると人間関係の修復は難しいため、必ず全員の同意を確認することが大前提です。
低価格での売却が贈与税とみなされる
「とにかく処分したい」と焦って相場より大幅に安い金額で売却すると、別の問題が発生します。
税務上、適正価格との差額が贈与とみなされる場合があるのです。
知らずに進めると余計な税金負担を抱えるリスクがあります。
相場より著しく安い価格での売却
適正価格2,000万円の不動産を1,000万円で売却した場合、差額の1,000万円が「贈与」と判断される可能性があります。
これにより、売却代金を受け取った共有者だけでなく、全員に課税リスクが及ぶこともあるのです。
「安く売れば楽」では済まないことを理解しておく必要があります。
贈与税リスクを回避する方法
贈与税リスクを避けるには、まず相場価格を正しく把握することです。
不動産会社の査定や、不動産鑑定士の評価をもとに、妥当な金額で売却すればリスクは軽減できます。
また、第三者を介した売却であれば「適正な市場取引」とみなされやすく、安心です。
共有者の一人が居住して家賃を払わない
共有名義の家に、一部の共有者が住み続けるケースもあります。
このとき家賃を払わないまま利用すると、他の共有者から不公平感が強まります。
この問題は「使用利益の不公平」としてトラブル化しやすいのです。
「使用利益の不公平」が原因
共有者が自宅として使っているにもかかわらず、他の共有者に家賃を支払わない場合、利益の偏りが生じます。
これにより「不公平だ」との主張が起こり、関係悪化につながります。
裁判所も不公平な利益配分があれば調整を命じる可能性があります。
法的対応と実務的解決策
解決策としては、居住者が他の共有者に対して使用料相当額を支払う方法があります。
話し合いで解決できなければ、調停や訴訟で支払いを求めることも可能です。
専門家を介してルール化しておくと、今後のトラブル予防にも役立ちます。
「売却できない」状況を打開するための解決策
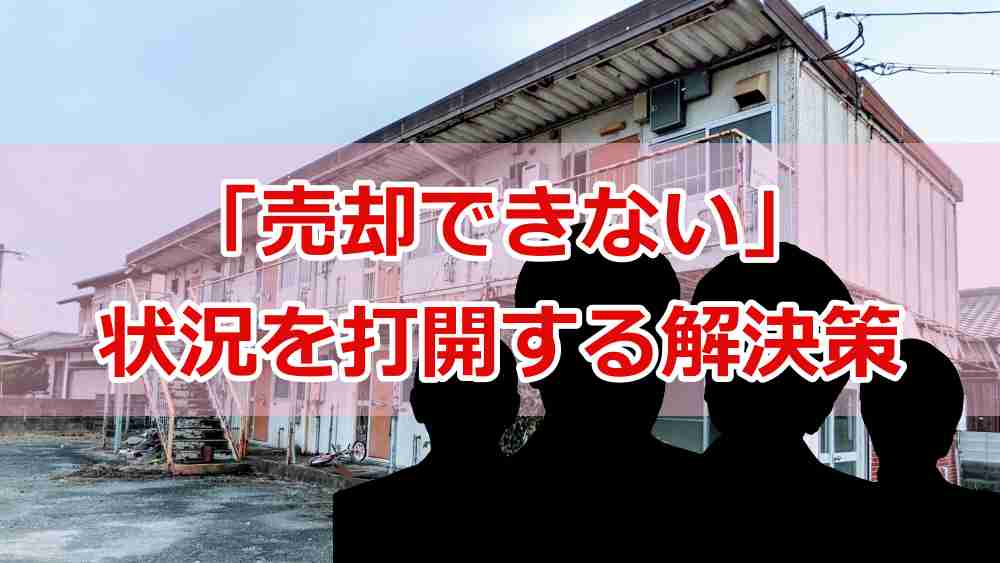
「共有名義 売却 できない」と悩んでいても、方法がないわけではありません。
法律上、いくつかの手段が用意されており、ケースに応じて選択することで前に進むことが可能です。
ここでは代表的な解決策を整理して解説します。
共有者全員の同意を得て売却する
最も王道の方法は全員の同意を得ることです。
時間はかかりますが、確実に売却を成立させることができます。
ただし、連絡調整や書類準備の手間は大きくなるため、事前の計画性が求められます。
全員の署名・押印が基本
売買契約書には、共有者全員の署名と実印が必要です。
誰か一人でも欠けると、契約は成立しません。
そのため、共有者が多いほど準備に時間がかかるのが現実です。
委任状を活用する方法
遠方に住んでいる共有者や、当日立ち会えない人がいる場合は委任状が役立ちます。
実印の押印と印鑑証明書を添付すれば、代理人に手続きを任せられます。
ただし、内容が不明確な委任状はトラブルの原因になるので注意が必要です。
自分の持分のみ売却する
他の共有者の同意が得られない場合でも、自分の持分を単独で売却することは可能です。
ただし実務上は買い手が限られるため、成立のハードルは高めです。
それでも「同意不要」という点は大きなメリットです。
同意不要で可能
法律上、自分の持分を他者へ売却するのは自由です。
契約の際に他の共有者の承諾は必要ありません。
早く動きたい人にとっては有効な手段といえます。
第三者が買い手になりにくい理由
しかし持分だけを購入しても、他の共有者との合意がなければ自由に利用できません。
このため第三者が買い手になる可能性は低いのが実情です。
実務的には、専門の買取業者に相談するのが現実的です。
他の共有者に売却する
同意が得られないなら、他の共有者に買い取ってもらうのも有効な手段です。
特に持分を増やしたい共有者にとっては歓迎されるケースがあります。
ただし税金面には注意が必要です。
持分を増やしたい共有者には有効
例えばリフォームや建替えを検討している共有者にとっては、持分拡大は大きなメリットです。
そのため交渉がスムーズに進みやすいという利点があります。
「互いの利益が一致」すれば早期解決が可能です。
譲渡所得税のリスク
ただし売却益が出た場合、譲渡所得税が発生することを忘れてはいけません。
また、売却価格が低すぎると贈与税扱いになる可能性もあります。
税理士や専門業者に相談しながら進めることが重要です。
土地の場合は分筆して単独名義にする
土地であれば、共有部分を分筆して個別の名義にする方法があります。
これにより、自分の部分を自由に売却できるようになります。
ただし形状や広さによっては売却が難しくなることもあるため注意が必要です。
土地家屋調査士による手続き
分筆には土地家屋調査士による測量・登記手続きが必要です。
一定の費用と時間がかかるため、事前に見積もりを確認しておきましょう。
準備を進める際には、不動産会社とも相談すると安心です。
形状や面積による売却難化のリスク
分筆後の土地が狭小地や変形地になると、買い手がつきにくくなります。
結果として売却価格が相場より下がるケースもあります。
事前に売却可能性や相場を確認してから進めるのが安全です。
共有物分割請求訴訟を利用する
最後の手段は共有物分割請求訴訟です。
裁判所に分割方法を判断してもらうことで、行き詰まった共有状態を解消できます。
ただし時間や費用、人間関係の悪化リスクも伴います。
裁判所に分割方法を判断してもらう
裁判所は「現物分割」「換価分割(売却して代金を分ける)」など、最適と考えられる方法を決定します。
強制力があるため、反対者がいても最終的には進められるのがメリットです。
どうしても合意が取れない場合の切り札といえます。
時間・費用・人間関係への影響
訴訟には長期間と高額な費用がかかります。
また親族間訴訟では人間関係が壊れる可能性も高くなります。
そのため、本当に必要な場合に限定して選択するのが望ましいでしょう。
共有名義不動産を売却するときの注意点
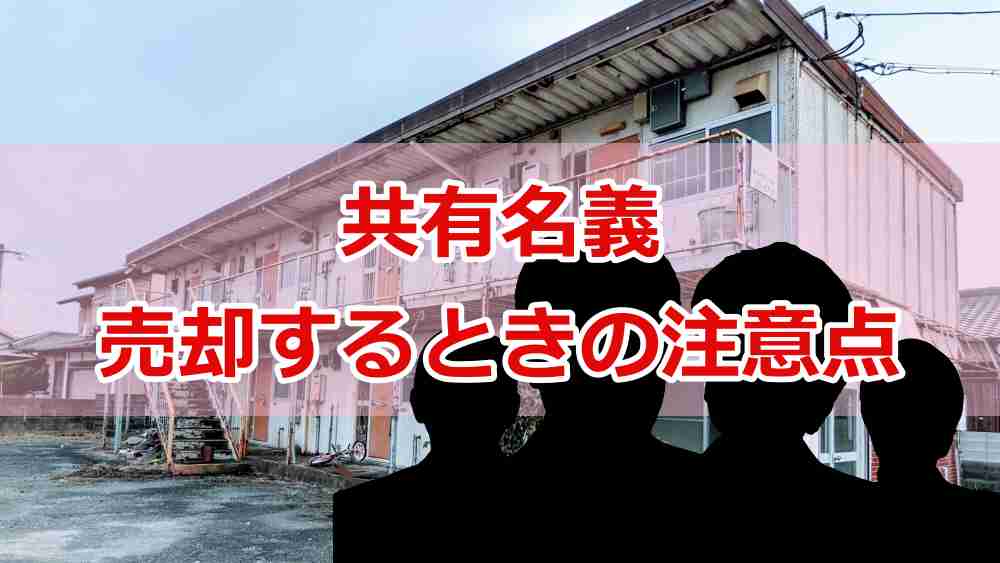
共有名義の物件を売却する際には、単独名義では発生しない独特のリスクが潜んでいます。
準備不足のまま進めると、思わぬトラブルや税務負担に直結するため、事前に押さえておくことが不可欠です。
① 全員分の必要書類を揃える
売却契約では、共有者全員の同意と書類提出が必須です。
以下を揃えられないと売却自体が進められません。
- 実印・印鑑証明書・住民票(共有者ごと)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
特に遠方に住む共有者や連絡が取りにくい相続人の分が欠けやすいため、早めの確認・回収が重要です。
② ローン残債がある場合の対応
共有不動産にローンが残っている場合、売却代金での完済が前提となります。
- 売却代金で残債を清算する流れを金融機関と確認
- 売却額が不足する場合の不足分の負担割合を事前に取り決める
負担調整が曖昧なまま契約すると、引渡し直前にトラブル化することが多いため注意が必要です。
③ 持分割合と税務リスク
売却代金を持分割合どおりに分配しないと、税務上「贈与」とみなされるリスクがあります。
- 持分1/2ずつであれば、代金も1/2ずつが原則
- 不公平な配分 → 贈与税課税の可能性
税額は想定以上に大きくなる場合があるため、税理士への事前相談が安心です。
④ 合意形成と事前準備
最も多いトラブルは「誰がどの条件で合意しているのか」が不明確なケースです。
- 配分・負担割合は文書化して記録を残す
- 調整役を一人決め、窓口を一本化する
共有者が多い場合や感情的対立がある場合は、弁護士や司法書士の関与で進行をスムーズにできます。
──これらの注意点を押さえておくことで、共有名義不動産の売却を無駄な手戻りなく安全に進めることが可能になります。
放棄を選ぶ場合の税金・費用リスク
共有持分を放棄すると、登録免許税(固定資産税評価額×2%)の負担や贈与税扱いになるケースがあります。
また「固定資産税や管理費から本当に解放されるのか?」という点も誤解が多く、自己判断は危険です。
詳しくは 共有持分 放棄 早い者勝ち?順番・やり方・最悪回避の判断軸を解説 をご覧ください。
共有持分を放棄する場合の手続き・流れ
共有持分の放棄を選ぶ場合、売却とは異なる実務的な段取りが必要です。
基本的には共有者の確認 → 登記申請 → 税金処理 → 確定申告という流れをたどります。
登記には委任状・印鑑証明・住民票などの書類が必須で、専門家(司法書士・弁護士)へ依頼するのが一般的です。
流れを整理した詳細解説は 共有持分 放棄 早い者勝ち?順番・やり方・最悪回避の判断軸を解説 にまとめていますのでご参照ください。
共有名義の売却を成功させるポイント

「共有名義 売却 できない」と悩む方は多いですが、実際には成功に近づくコツがあります。
ポイントは「準備の早さ」と「専門家のサポート」をどう活用するかです。
ここでは、具体的な工夫や制度の活用方法を紹介します。
売却までの平均期間と早めの準備
共有名義は意思統一に時間がかかるため、通常の不動産売却より長期化しやすいのが特徴です。
調査データを踏まえると「早めの準備」がどれほど重要かがわかります。
遅れるほどトラブルの芽が増えてしまうため、行動開始のタイミングがカギです。
LIFULL調査での平均期間
LIFULL HOME’Sの調査では、共有名義の売却完了まで1年以上かかる人が24.8%もいました。
通常の売却に比べて時間がかかるのは、やはり合意形成と書類準備が難しいからです。
これを知っておくことで、想定外の遅れにも対応できます。
なぜ早めの動き出しが必要か
「売ろう」と決めても、実際に契約できるまでに多くの調整が必要です。
特に遠方の共有者や高齢の共有者がいる場合は、署名・押印の準備に時間がかかります。
1年以上先を見据えて動き出すことが、成功の第一歩です。
不在者財産管理人制度の活用
共有者の中に行方不明の人がいると、売却はストップしてしまいます。
このような場合に活用できるのが「不在者財産管理人制度」です。
家庭裁判所を通じて、代わりに意思表示をしてくれる人を選任できます。
行方不明の共有者がいる場合
相続で共有者が増え、誰かの所在が不明になることは珍しくありません。
連絡が取れなければ売却は進まず、固定資産税などの負担だけが続きます。
そんな時に不在者財産管理人を利用するのです。
家庭裁判所での手続き方法
家庭裁判所に申し立てを行い、管理人を選任してもらいます。
この手続きには数か月かかるため、早めの準備が重要です。
「行方不明者がいる=売れない」ではないことを知っておくと安心です。
専門家の活用
共有名義の売却は、専門知識がないと手続きや税務でつまずきがちです。
不動産会社だけでなく、司法書士・税理士・弁護士を適切に組み合わせて活用しましょう。
結果的に時間短縮やトラブル回避につながります。
不動産会社の役割
売却活動の窓口となり、買主探しから契約締結までを担います。
特に共有名義に強い不動産会社を選ぶことで、交渉の進行もスムーズになります。
実績豊富な会社を選ぶのが成功の秘訣です。
司法書士・税理士・弁護士の関与
司法書士は登記手続き、税理士は税金対策、弁護士は共有者間のトラブル解決をサポートします。
それぞれの専門領域を組み合わせることで、総合的に安全な売却が可能になります。
費用はかかりますが、安心感と成功率の高さで十分に見合う投資です。
相続時に共有名義を避ける工夫
根本的にトラブルを防ぐには、相続時に「共有名義にしない工夫」が大切です。
遺産分割の段階で単独名義にしておけば、将来的な売却もスムーズになります。
ここでは代表的な方法を紹介します。
代償分割による単独名義化
1人が不動産を相続し、他の相続人にはその分の金銭を支払う方法です。
これにより、不動産は単独名義になり、後の売却も簡単にできます。
相続時点で資金を用意できるかどうかがポイントです。
換価分割で売却後に分配する方法
不動産を売却し、その代金を相続人で分ける方法です。
この方法なら、共有状態を避けられます。
「現金で分ける」という明快さがメリットです。
まとめ:共有名義でも不動産売却の道はある
「共有名義だから売却できない」と感じている方も多いですが、実際には複数の解決策があります。
全員の同意を得るのが難しい場合でも、持分のみの売却や分筆、さらには裁判所の制度を活用することで前に進む道は開けます。
大切なのは「時間が経つほど複雑になる」という現実を踏まえ、早めに専門家に相談することです。
不動産会社や司法書士、税理士、弁護士といった専門家の力を借りることで、トラブルを回避しながら安心して手続きを進めることができます。
「共有名義でも売却は不可能ではない」──この視点を持ち、行動するかどうかが成功への分かれ道です。![]()
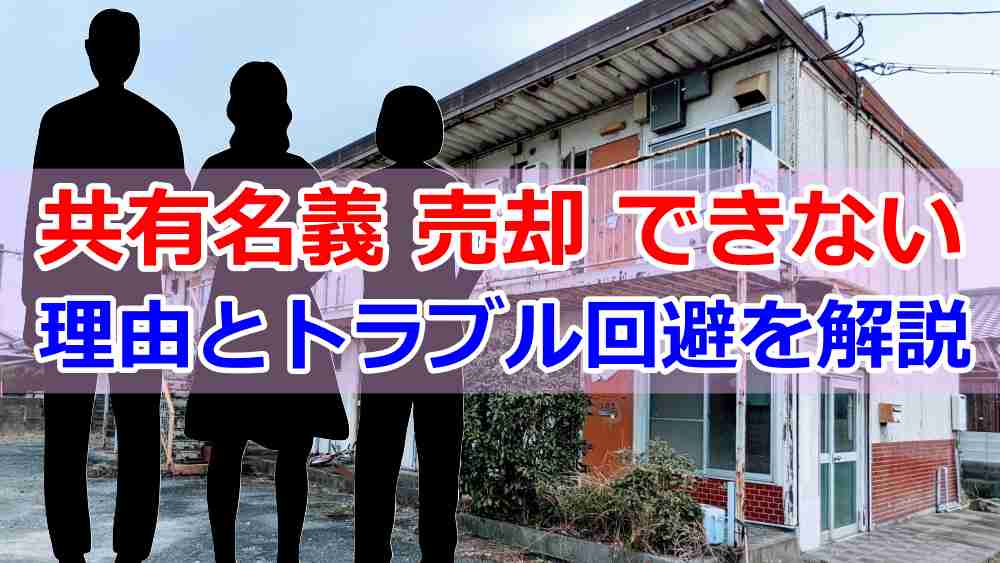

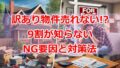
コメント